開沼 博
添い寝したり、散歩したりといったJKビジネスの裏で、「裏オプ」(裏のオプション)として行われている少女売春。その実態について社会学者の開沼博氏は「現代社会の本質が凝縮している」と語る。

3.11から6年。いまだに福島第一原発を巡っては誤報やデマが頻発し、福島の復興を遅らせ、廃炉作業の足も引っ張っている。廃炉が一筋縄でいかないことは事実。しかし、事実を正確に知ったうえで、「性急に判断せずに粘り強く議論を続ける」姿勢が醸成されれば、道は開けていくはずだ。

3.11から6年。いまだに福島第一原発を巡っては誤報やデマが頻発し、福島の復興を遅らせ、廃炉作業の足も引っ張っている。廃炉が一筋縄でいかないことは事実。しかし、事実を正確に知ったうえで、「性急に判断せずに粘り強く議論を続ける」姿勢が醸成されれば、道は開けていくはずだ。

最終回
2015年2月11日。福島県福島市で、除染や放射線に関して、地元で生活するさまざまな立場の人が意見交換する「ポジティブカフェ」が開かれた。最終回は、前回、前々回を踏まえて、福島県在住の詩人であり、高校の国語教師でもある和合亮一氏と、開沼博氏の対話をお送りする。

第2回
3.11から5年目を迎えてもなお、福島は未解決の課題で山積みだ。福島には安易に触れてはいけないという思いが、向き合うべき課題から目を背けることにつながってはいないだろうか。震災以前から原発問題を論じ、震災以後、福島の課題と対峙し続ける開沼博が、市民との対話を通してその現状を探る。

3.11から5年目を迎えてもなお、福島は未解決の課題で山積みだ。福島には安易に触れてはいけないという思いが、向き合うべき課題から目を背けることにつながってはいないだろうか。震災以前から原発問題を論じ、震災以後、福島の課題と対峙し続ける開沼博が、市民との対話を通してその現状を探る。

第508回
26日、震災後初となる福島県知事選の投開票が行われた。事前予想の通り、前福島県副知事の内堀雅雄氏が当選。福島のみならず日本の未来を占う重大な選挙だったが、投票率はワースト2位を記録し、関心が高いとは言えない結果となった。県民は内堀氏に何を期待したのか。社会学者の開沼博が総括する。

第22回
AV女優も「いいね!」集めも根っこは同じ失われゆく価値といかに向きあうべきなのか【社会学者・鈴木涼美×社会学者・開沼博】
『「AV女優」の社会学』の著者として話題を呼ぶ鈴木涼美と開沼博の対談。「女子高生」の“値札”を失ってから、その寂しさをいかに埋めればよいのか。Facebookの「いいね!」集めやパワースポット通い、ホストに入れこむのと同様に、AV女優という仕事がその一つになっていると鈴木は語る。
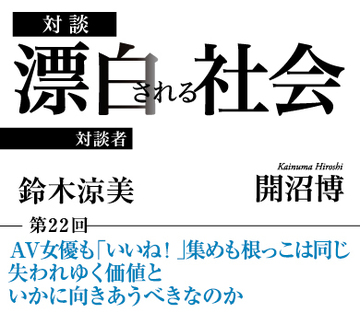
第21回
AV女優への偏見こそが仕事の価値を生んでいる 「女子高生」ほどわかりやすい“値札”はない【社会学者・鈴木涼美×社会学者・開沼博】
『「AV女優」の社会学』の著者として話題を呼ぶ鈴木涼美と開沼博による対談。AV女優に対する偏見と、裸が猥褻物であるという事実が、AV女優という仕事の価値を高めていると鈴木は語る。100円の下着が8000円で売れた「女子高生」ブランドを失ったとき、鈴木は何を思ったのか。
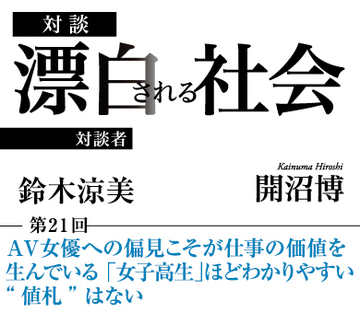
第499回
10月26日、震災後初の福島県知事選が投開票を迎える。前副知事の内堀雅雄氏が優位とされる「一強多弱」の見方が強く、また多党が内堀氏に相乗りして争点がわかりづらいこともあり、関心が高いとは言えないのが現状だ。福島県知事選の何に注目すべきなのか。社会学者の開沼博がその全貌を読み解く。

第20回
自ら語ることで女の子は「AV女優」に変わる 彼女たちはなぜ、AVの世界を選んだのか【社会学者・鈴木涼美×社会学者・開沼博】
『「AV女優」の社会学』の著者として話題を呼ぶ鈴木涼美と開沼博による対談。女の子たちはなぜ、AV女優になることを選び、どのようにAV女優へと変わっていくのだろうか。そこには、面接という商業的な仕組みのなかで自らを語り続けることで、普通の女の子がAV女優に変貌する構造があった。

第486回
11日、政府は「吉田調書」を公開した。朝日新聞の木村伊量社長が、調書に関する報道の誤りを認めて記事を取り消し、謝罪したことは大きな話題を呼んでいる。被災地不在のメディア・イベントはいかに成立したのか。調書公開に至るまでの過程を検証し、震災報道が抱える本質的問題を開沼博が指摘する。
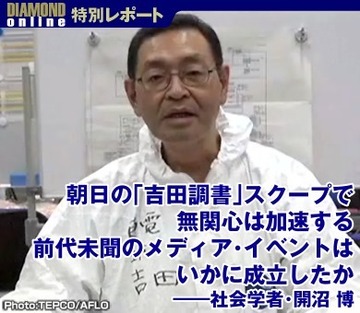
第485回
9月11日、非公開とされていた「吉田調書」が公開された。きっかけとなった朝日新聞の記事の真偽をめぐって報道合戦は過熱し、調書を取り巻く議論は本質を見失っているのが現状だ。私たちは、吉田調書の公開をどのように捉えるべきなのか。『「フクシマ」論』で衝撃を与えた社会学者、開沼博が語る。
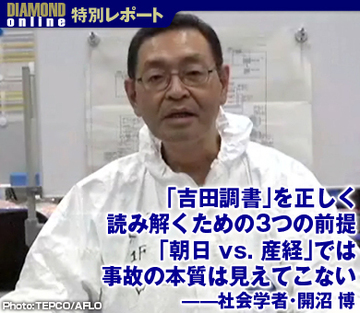
最終回
東日本大震災から4年目を迎える「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。事業を通じた震災復興への貢献にその可能性を見出す。最終回では、企業による支援の課題と可能性を総括したうえで、被災地の内側からの取り組みとして「夜明け市場」を紹介する。
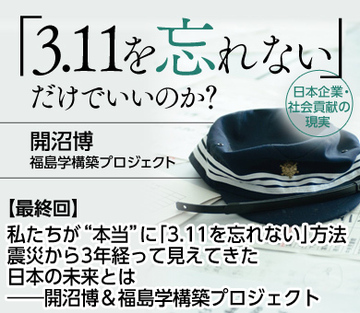
第7回
東日本大震災から4年目を迎える「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。事業を通じた震災復興への貢献にその可能性を見出す。企業から優秀な人材を派遣してもらうために、何をすべきなのか。被災地と企業をつなぐ取り組みをされている藤沢烈氏との対談。

第6回
東日本大震災から4年目を迎えて「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。事業を通じた震災復興への貢献にその可能性を見出す。今回は、時間の経過とともに変化する被災地のニーズを的確に把握したうえで、後方支援に尽力するJTの取り組みを紹介する。

第5回
東日本大震災から4年目を迎える「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。事業を通じた震災復興への貢献にその可能性を見出す。今回は、ツアーを通して被災地と観光客をつなぐことでビジネスとしても成功を収める、旅行会社JTBの取り組みに迫った。
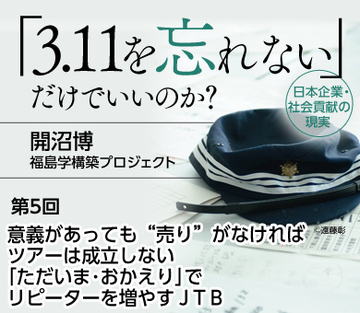
第4回
東日本大震災から4年目を迎える。1000年に一度の災害、敗戦以来の歴史的事件と言われ、「絆」「がんばろう」と多くの人が叫んでいた。「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。復興支援に関わりたい企業が躊躇する理由をひも解き、解決策を提示する。

第3回
東日本大震災から4年目を迎える。1000年に一度の災害、敗戦以来の歴史的事件と言われ、「絆」「がんばろう」と多くの人が叫んでいた。「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。震災直後から被災地で継続支援を行う人材会社パソナの活動と想いに迫る。
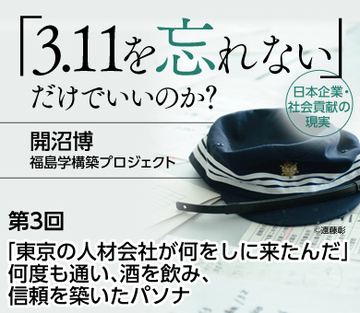
第2回
東日本大震災から4年目を迎える。1000年に一度の災害、敗戦以来の歴史的事件と言われ、「絆」「がんばろう」と多くの人が叫んでいた。人は「3.11を忘れてはならない」と繰り返すが、それだけで風化に抗うことはできるのか。IT業界から財団まで第2回では、震災後に実施された各団体による復興支援の姿を追う。
