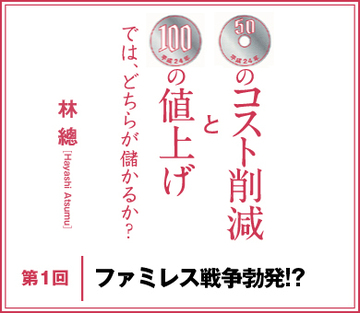猪木はインスタントコーヒーを入れながら、ヒカリに話しかけた。
「ボクは取締役ですごく忙しいのに、秘書がつかないんだ。だからコーヒーを入れるのも、出張の手配もすべて自分でするんだ。勉強の時間を見つけるのが大変だよ」
猪木はコーヒーカップをヒカリに手渡すと、ソファに腰を下ろした。
「最初に言っておくけど、君を実習生として受け入れるなんて先週まで知らなかったんだ。うちの会社は4月決算だから、いま忙しいんだよ。社長と安曇先生が勝手に決めたことだから断るわけにはいかないしね――」
ヒカリには、それが何を意味しているのか見当もつかなかった。
「安曇先生とは卒業以来会ってないんだ。それに、ボクは安曇ゼミの落ちこぼれでね、3年になったときに辞めたんだ――」
「ホントですか?」
「ウソなんか言わないよ。ボクはほかの誰よりも勉強したし、知識の多さは負けない自信があった。だけど、先生はクラークシップを経験しないと単位はやらないって言うんだ。おかしいよね。だから辞めた。もう10年以上も前のことだけどね」
そう言うと、猪木は熱いコーヒーを音を立ててすすった。
「君は経営コンサルタントになりたいんだってね。社長から聞いたよ」
「安曇先生ではないんですか?」
「まさか。さっき言ったでしょ。ボクは先生とは連絡をとっていないって。たまたま勤めたこの会社の社長が先生の友だちだったというだけのことだ」
「そんな……」
「ボクは大学を卒業して外資系のコンサルティング会社に入社した。そこで、3年働いたあと、別のコンサルティング会社に移って、そのあと、まあいろいろとあってさ。この会社の社長に呼ばれたんだ。ボクの経験から言わせてもらうなら、クラークシップなんて時間のムダさ。それに管理会計なんてチョロいもんだよ」
猪木の話を聞きながら、もしかすると猪木は安曇に悪感情を抱いているのではないか、とヒカリは思った。
「君は本当にこの会社で実習をするつもりなの?」
「ええ」
もちろんそのつもりだ。学生時代に経営の経験なんて、そうそうできるものではない。