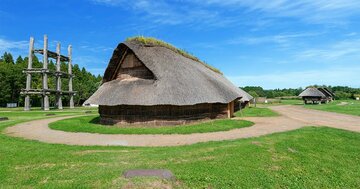耐性菌の登場
その後、多くの抗生物質が見つかり、現在では抗生物質はごくありふれた薬となっている。人類を苦しめてきた結核、ペスト、チフス、赤痢、コレラなどの伝染病は、私たちから去っていったかのように見えた。
しかし、人類が安心したのも束の間、細菌は素早く逆襲を開始した。抗生物質の効かない「耐性菌」が出現してきたのだ。耐性菌のなかで、院内感染などで現在もっとも問題になっているのが「メチシリン耐性黄色ブドウ球菌」(MRSA)だ。メチシリンは耐性菌に強い抗生物質として登場したが、これさえも効かない黄色ブドウ球菌がMRSAである。
抗生物質「バンコマイシン」は一九五六年に使われ始め、四十年以上も耐性菌が現れず、MRSAに対する切り札だった。ところが二十世紀末に、バンコマイシン耐性腸球菌の出現が報告された。その後もさらにバンコマイシンに耐性を持つ菌が見つかってきている。
現在、最後の砦となっているのは、二〇〇〇年に発売されたリネゾリド。これは合成物質で、いままでのものとはまったく異なるしくみによって細菌の増殖を抑える。日本国内におけるリネゾリド耐性のMRSAの報告例は極めてまれだが、海外では散見されている。
耐性菌を生む一つの原因は抗生物質の多用と考えられている。たとえば、抗生物質はウイルスには効かないので、風邪には、明らかに細菌感染が疑われるときにのみ処方すべきだ。耐性菌のできにくい新しい抗菌薬の開発など、病原細菌との果てしない闘いは続いている。
(※本原稿は『世界史は化学でできている』からの抜粋です)
好評連載、人気記事
☆ マリー・アントワネットも悩まされた、ベルサイユ宮殿の残念な真実
☆ 古代エジプト、ピラミッド建設の労働者の意外すぎる給料
☆ 意外に知らない…金の産出量が最も多い国とは?
東京大学非常勤講師
元法政大学生命科学部環境応用化学科教授
『理科の探検(RikaTan)』編集長。専門は理科教育、科学コミュニケーション。一九四九年生まれ。千葉大学教育学部理科専攻(物理化学研究室)を卒業後、東京学芸大学大学院教育学研究科理科教育専攻(物理化学講座)を修了。中学校理科教科書(新しい科学)編集委員・執筆者。大学で教鞭を執りつつ、精力的に理科教室や講演会の講師を務める。おもな著書に、『面白くて眠れなくなる化学』(PHP)、『よくわかる元素図鑑』(田中陵二氏との共著、PHP)、『新しい高校化学の教科書』(講談社ブルーバックス)などがある。