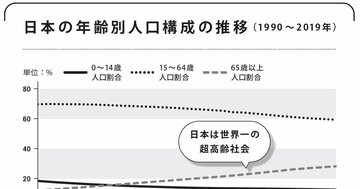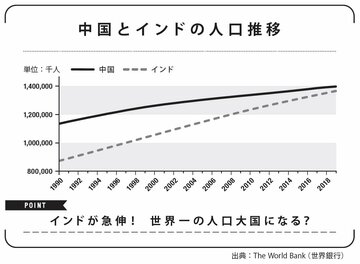世界の「今」と「未来」が数字でわかる。印象に騙されないための「データと視点」
人口問題、SDGs、資源戦争、貧困、教育――。膨大な統計データから「経済の真実」に迫る! データを解きほぐし、「なぜ?」を突き詰め、世界のあり方を理解する。
書き手は、「東大地理」を教える代ゼミのカリスマ講師、宮路秀作氏。日本地理学会の企画専門委員としても活動している。『経済は統計から学べ!』を出版し(6月30日刊行)、「人口・資源・貿易・工業・農林水産業・環境」という6つの視点から、世界の「今」と「未来」をつかむ「土台としての統計データ」をわかりやすく解説している。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「原油はあと30年で枯渇する!」って本当?
地球上に存在する原油の絶対的な埋蔵量のうち、採算が取れて利益が出ると判断された油田の埋蔵量を可採埋蔵量といいます。また可採埋蔵量を1年間の産油量で割ったものを可採年数といいます。
50年近く前は「可採年数はあと30年しかない!」といわれていたそうですが、今も産油は続いています。これはいったいどういうことなのでしょうか?
可採埋蔵量は技術的・経済的概念で考えられる量です。
石油・天然ガスなどのエネルギー資源は、埋蔵している場所を探査しなければ採掘できません。探査や採掘、生産に関する技術革新が進み、コストが低くなっていけば、可採埋蔵量は今後も増加していくと考えられています。
実際に探査技術が進歩して、新しい油田やガス田が発見されています。原油に関していえば、1980年以降、可採年数は40年程度を維持してきました。
2019年時点での原油の可採埋蔵量は約2676億㎘、可採年数は57.6年です。国別で見ていきましょう。
世界で最も埋蔵量が多いのはベネズエラで、可採埋蔵量は481億㎘。可採年数(可採埋蔵量÷2019年の産出量)はなんと954.7年もあります。その他の上位国はどこでしょうか?