メール、企画書、プレゼン資料、そしてオウンドメディアにSNS運用まで。この10年ほどの間、ビジネスパーソンにとっての「書く」機会は格段に増えています。書くことが苦手な人にとっては受難の時代ですが、その救世主となるような“教科書”が今年発売され、大きな話題を集めました。シリーズ世界累計900万部の超ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者であり、日本トッププロのライターである古賀史健氏が3年の年月をかけて書き上げた、『取材・執筆・推敲──書く人の教科書』(ダイヤモンド社)です。
本稿では、その全10章99項目の中から、「うまく文章が書けない」「なかなか伝わらない」「書いても読まれない」人が第一に学ぶべきポイントを、抜粋・再構成して紹介していきます。今回は、文章を書くうえで極めて大切な「読む力」について。(写真/兼下昌典)
 『取材・執筆・推敲』の著者・古賀史健が2021年に開校した「バトンズ・ライティング・カレッジ」
『取材・執筆・推敲』の著者・古賀史健が2021年に開校した「バトンズ・ライティング・カレッジ」
ヘタな絵描きの絵はすぐ完成する
文章がつまらない人には、わかりやすい共通点があります。
そのポイントを考えるにあたって紹介したいのが、黒澤明監督の告白です。
黒澤明──『七人の侍』や『羅生門』、『生きる』など、世界の映画史に燦然と輝く傑作群を残した映画監督です。
よく知られるように彼は、もともと絵描きをめざしていた人物でした。実際、彼の残した絵コンテは画集として出版されるほど芸術性にすぐれています。絵コンテでこのクオリティなのだから、本気で絵を描いたらどうなるのかと思ってしまうほどです。いったいなぜ、絵の道をあきらめたのか。晩年のインタビューで彼は、その理由を「描く技術」ではなく、対象を見る「目」に求めています。
──おもしろい話しましょうか、絵ってねえ、たとえばセザンヌでも誰でも長いことかかって絵を描いてるでしょ? 下手な絵描きっていうのはすぐ絵ってできちゃうんだよ。あんなには描いてはいられないんですよ。ということはねえ、あの人達が見てるものを僕達は見てないわけ、あの人達が見えてるものは違うんですよ。だからあんだけ一生懸命描いてるんですよね。自分に本当に見えてるものを本当に出そうと思って。僕達にはじつに浅はかなものしか見えてないからすぐにできちゃうわけ。──
(『黒澤明、宮崎駿、北野武──日本の三人の演出家』ロッキング・オン刊より)
まず鍛えるべきは「読む力」
つまり、こういうことです。
すぐれた画家たちは、画力以前に「目」がすぐれている。凡人には見えないものを、ありありと見ている。だからひとつのモチーフを長い時間かけて描き続けるし、それに飽きることがない。一方、自分(黒澤)のような凡人は、すぐに描き上げてしまう。筆が速いのではない。一流の画家たちに見えているものが見えていないから、すぐに描き上げてしまうのだ。ほんとうはまだ、描き上げてはいけないのだ。見る(読む)べき対象は、もっとあるのだ。
この発言に触れたとき、ぼくはライターもまったく同じだと膝を打ちました。鍛えるべきは「書く力」ではありません。まずは「読む力」を鍛えてこそ、すぐれた書き手たりえるのです。
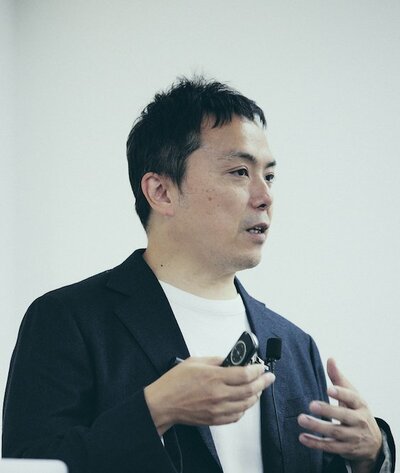 古賀史健(こが・ふみたけ)
古賀史健(こが・ふみたけ)1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。メガネ店勤務、出版社勤務を経て1998年にライターとして独立。著書に『取材・執筆・推敲』のほか、31言語で翻訳され世界的ベストセラーとなった『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(岸見一郎共著、以上ダイヤモンド社)、『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』(糸井重里共著、ほぼ日)、『20歳の自分に受けさせたい文章講義』(星海社)など。構成・ライティングに『ぼくたちが選べなかったことを、選びなおすために。』(幡野広志著、ポプラ社)、『ミライの授業』(瀧本哲史著、講談社)、『ゼロ』(堀江貴文著、ダイヤモンド社)など。編著書の累計部数は1300万部を超える。2014年、ビジネス書ライターの地位向上に大きく寄与したとして、「ビジネス書大賞・審査員特別賞」受賞。翌2015年、「書くこと」に特化したライターズ・カンパニー、株式会社バトンズを設立。2021年7月よりライターのための学校「バトンズ・ライティング・カレッジ」を開校。
読者としての自分が甘すぎる!
支離滅裂な原稿を書いてしまうライター。要領を得ない、ピントのずれた原稿を書くライター。及第点以上の原稿を書けず、伸び悩んでいるライター。ぼくに言わせると彼らは、等しく技術以前のところでつまずいています。
ひと言でいって、「読者としての自分」が甘すぎるのです。
まず、取材対象を「読む」ことができていない。表面的な理解にとどまり、その根底にあるもの、奥にあるもの、あるいは裏側にあるものを、見ようとしていない。なにもわかっていないのに、わかったつもりで書いている。
そして致命的なことに、自分の原稿を「読む」ことができていない。40点でしかない自分の原稿に、ぼんやり80点をつけている。40点のまま、筆を擱いてしまっている。「読者としての自分」が厳しければ、40点の原稿を40点として、正確に評価することができるはずです。そして自分の現在地さえわかってしまえば、そこから80点や90点の原稿をめざして、まっとうな努力を続けられます。けれども「読者としての自分」が甘すぎる結果、自分の原稿が読めない。これでいいやと思ってしまっている。上達するはずがありません。
小手先のテクニックよりも、
はるかに大切なこと
ひとつの原稿を書き終えたとき、ぼくにとって「古賀史健」という読者は、かなり厄介な存在です。容赦なくダメ出しをして、書きなおしを要請してきます。それは「書き手としての自分」がそうさせているのではなく、「読者としての自分」がそうさせるのです。彼(読者としての自分)が目を光らせているかぎり、でたらめな原稿をそのまま世に出すことはありません。逆に言うと、「読者としての自分」が甘くなってしまった途端、ぼくはプロのライターではいられなくなるでしょう。
ライターにかぎらず、人に読ませる文章を書くのであれば、小手先の表現テクニックを学ぶよりも先に、「読者としての自分」を鍛えていきましょう。たくさんの本を読み、映画を、人を、世界を、「読む」人になりましょう。あなたの文章がつまらないとしたら、それは「書き手としてのあなた」が悪いのではなく、「読者としてのあなた」が甘いのです。
(続く)



