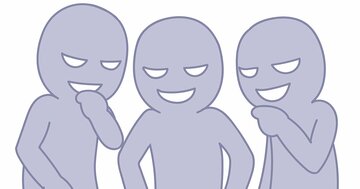減点法の日本社会で消える自分らしさ
よくよく、考えてみようと思います。いつから、私が自分のことを信用できなくなったのか。いつから、私が自信を持てなくなってしまったのか。
ちゃんと思い出そうとすると、記憶が蘇ってきます。社会人になったばかりの頃、大学生の頃、受験をしていた頃、高校生の頃、中学の思春期の頃、小学生の頃、幼くて何も考えていなかった頃、遠い記憶……。
あ、そうだ。たしか、私は、高校生の頃は、きちんと自信を持てていたような気がする。むしろ、自信満々だったと言ってもいい。
そうです。私は自信満々だったのです。あの頃。高校生の頃。自分には何でもできるんだと思っていたし、自分を救ってくれるのは自分しかいないと思い込んでいました。
高校生の頃の私にとって、「自分」とは、信頼のおける素晴らしい存在でした。そして、私がコントロールできる存在だと思っていました。私と「自分」は同じ人間で、私は「自分」のことをきちんと操作できる。私が向かせたい方向に向かせられる。私が困った時には、私は、私のことを信じることができていました。私は、過去の自分も全部受け止めていたし、未来の自分も、きっとなんとかうまいことやってくれるんだろうと、ちゃんと信頼することができていました。あの頃は。
高校生の頃の「自分」は、きちんとした信念を持っていて、矜持があって、そして、愛情深い人間でした。友達が困ったことがあればちゃんと助けてあげられる。支えてあげられる。テレビで災害のニュースが流れれば、心を傷めることができる。いじめの事件があった、いじめの事実を知っていたのにそれを担任の教師は無視していた、と聞けば、その教師に対して怒りの感情を抱くことができる。どこか知らない遠くの国の貧しい子ども達のために、募金ができる。そういう人間だったんです。きちんとした。まっとうな価値観を持った、優しい人間だったはずなんです。
なのに、それが崩壊したのは、いつのことだったでしょうか。よく覚えていません。でも、私が気がついた時には、「自分」は全く信用できない存在になっていました。
もしかしたら、それがわかったのは、就活生の頃だったかもしれない。そう、そうです。思い出しました。ある寒い夜に、家を飛び出して、走ったことがあったんです。ただただ、無我夢中で。家の近くを……ではなくて、遠くまで。駅の方まで。とりあえず、走りました。疲れるまで、足を止めたくなるまで、走りました。たぶん夜中の3時くらいだったと思います。息が白くなっていて、自分の手が震えている光景をぼんやりと見ていたことを覚えています。寒かった。とても寒かった。
何しろ私は、ものすごい薄着でした。ぺらぺらのTシャツに、ゆるゆるのジャージに、高校のとき、文化祭で作ったパーカーを着ていました。背中にはクラス全員の名前が書いてあったような気がします。でもそんなダサい格好をしていることなんて全然気にしていませんでした。私は、泣いていました。涙を流しながら、とにかく、駅まで走り続けました。あまりに寒いので、涙が凍ってしまうんじゃないかと思いました。でも、凍りませんでした。走っているうちに、寒さなんて忘れてしまって、ただ、別のことを考えていたんです。
私は、今まで信じきっていた、「自分」のことを、考えていました。
あれ、自分って、なんだったんだろう。あれは、誰なんだろう。
私の心の中にいる、この、「自分」って。
「川代紗生」って、誰?
そう思ったんです。不安になりました。このよく信用もできない人間と、自分の心の中で共存していることにぞっとしました。赤の他人みたいに思えたんです。本当に。
どうしてそう思ったのでしょう。私は……私は、そう。そうだ。そうです。私は、あのとき、一番入りたかった会社に落ちたんです。ほとんど、あとが残っていなかった。いや、もっと正直に言えば、あとに残っているのは、本当に適当に練習がてら受けた小さな会社だけでした。私は広告代理店に行きたかった。それも、電通や博報堂のような大手の会社に行きたかった。コピーライターになりたかったんですよね。だから、そういう大きな会社で、大きなクライアントをかかえて、クリエイティブな仕事をしたかった。まあ、あの頃の私が、「クリエイティブ」という言葉の意味をきちんと理解していたかどうかは謎ですが。
それで……だから、私はとにかく、もう自分には何も残っていないんじゃないかと思った。信用できない、と思ったんです。自分のことが。こいつは誰? と本気で思いました。なんでこんなところにいるの? と思いました。二重人格者とか、そういうのじゃないんですが、単純に、「私」という意識が、「川代紗生」という人間のことを、理解できないと思ったんです。私って何なの? と思いました。私のことがよくわからなかった。本当によくわからなかったんです。それで、パニックを起こして、家を飛び出したんだと思います。