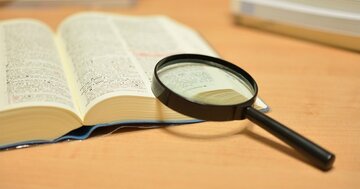Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
霊きゅう車は姿を消し、葬儀も家族だけで静かに行われるようになった。一方で、他人の死はメディアやSNSでセンセーショナルに扱われ、のぞき見の対象となっている。私たちはいつの間にか、自分の死からは目をそらし、他人の死を消費する社会をつくり上げてしまった。「死」は、いま静かにこの社会から姿を消そうとしている。※本稿は、小谷みどり『〈ひとり死〉時代の死生観「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日選書、朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。
死者は増えているのに
霊きゅう車を見なくなった
私たちは、この世に生を享けた瞬間から死に向かって生きている。言葉を換えれば、どの人も、今日が一番若く、明日明後日と、どんどん老いに向かっていく。
しかし赤ちゃんや子どもに対しては、周りの大人はその成長を喜び、子どもがどんどん老いや死に向かっていることを悲しんだりしない。
さらにいえば、日本では1990年以降、急速に死亡者人口が増加しているのに、多くの人はそれを実感していないだろう。
例えば、「子どもの頃は街中で霊きゅう車をよく見たのに、最近はとんと見なくなった」と言う人は少なくない。
数十年前に比べると、死亡人口は急増しているのに、街中で霊きゅう車を見る機会が減ったという事実は興味深い。
その理由は、かつてのような宮型霊きゅう車が減り、ぱっと見れば霊きゅう車とはわからないトヨタのエスティマなどを改造した霊きゅう車が主流になったことにある。霊きゅう車は街中でたくさん走っているが、私たちが気づかないだけなのだ。
火葬場が新設されるとき、近隣住民との話し合いで、宮型霊きゅう車の乗り入れを禁じる自治体が増えていることや、利用者自身も、派手な宮型霊きゅう車より、普通車に見える霊きゅう車を好む傾向が強いこともあり、宮型霊きゅう車が大幅に減っているのだ。