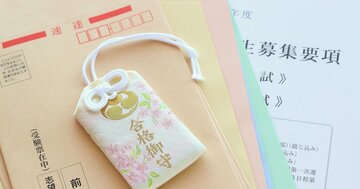働きながら3年で、9つの資格に独学合格! 大量に覚えて、絶対忘れないノウハウとは?
「忘れる前に思い出す」最強のしくみ、「大量記憶表」を公開!
本連載の著者は棚田健大郎氏。1年間必死に勉強したにもかかわらず、宅建試験に落ちたことをきっかけに、「自分のように勉強が苦手な人向けの方法を編み出そう」と一念発起。苦労の末に「勉強することを小分けにし、計画的に復習する」しくみ、大量記憶表を発明します。棚田氏の勉強メソッドをまとめた書籍、『大量に覚えて絶対忘れない「紙1枚」勉強法』の刊行を記念して、棚田氏の保有資格、マンション管理士に関する寄稿記事を公開します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
マンション管理士は「食える資格」なのか?
マンション管理士は、試験難易度は高いのもの、これまで独占業務がないことがネックと言われてきました。いわゆる宅建の「重説」のように、マンション管理士にしか許されていない業務が存在しなかったのです。
こういう資格のことを名称独占資格といい、マンション管理士と名乗るためだけに試験を受けていたのですが、この度の法改正によって、ついに独占業務ができるのではと言われております。
法律改正! 何が変わるの?
令和2年6月24日に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。これは、マンション管理士や管理業務主任者の試験範囲になっている法律です。
改正マンション管理適正化法では「マンション管理計画認定制度」が創設され、令和4年4月1日から施行されます。
また、令和3年9月28日に、国交省は、マンション管理適正化法の改正を受けて、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(基本方針)を定め(マンション管理適正化法3条)、マンション管理計画認定制度の認定基準を示しています。基本方針も令和4年4月1日に施行されます。
このマンション管理計画認定制度とは、いったいどんな制度なのでしょうか。
国から「お墨付き」をもらえる!
マンション管理計画認定制度とは、管理適正化推進計画を作成した地域において、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、マンション管理組合が地方公共団体から適切な管理計画を持つマンションとしての認定を受けることができる制度です。
認定には、マンションが所在する地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成していることが必要となります。
マンション管理適正化推進計画とは、地方公共団体が、国が定めた基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るために作成することのできる計画です。
つまり、「維持管理が計画的に行われているマンション」だというお墨付きをもらえる制度のことです。
では、認定してもらったらどんなメリットがあるんでしょうか。管理計画認定のメリットとしては、次のようなことが期待されています。
・住人の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持・向上しやすくなる
・適正に管理されたマンションであることが市場において評価される
・適正に管理されたマンションがあることで、地域価値の維持・向上に繋がる
どれも抽象的ですが、「ちゃんとしているマンションだよ」ということを客観的にアピールできます。なぜこんな認定制度ができたのでしょうか?
以前、限界マンションという言葉がニュースで踊っていました。築年数が古くなってくると、大規模修繕や耐震改修にかなりの費用が掛かるのですが、そのための費用をちゃんと積み立てられておらず、修繕したくてもできないマンションが増加傾向にあるんです。
こういうマンションの発生を予防するためには、将来を見据えて計画性を持った管理計画をたててそれに沿って運用していくことが急務だったことから、今回の認定制度の開始にいたったと考えられます。
この制度の目玉は何と言ってもいままで独占業務のなかったマンション管理士です。
まず主体となるのはマンションの管理組合です。管理組合が公益財団法人マンション管理センターを通して適切な管理が行えているかマンション管理士に確認してもらい、適切な管理が行われていれば、適合通知が届きます。
その適合通知を全国の市や東京特別区(町村は都道府県)に申請して認定を受けるという流れです。また、適正に管理されていないと判断されるマンションについては、自治体が指導・助言・勧告を行うことになっています。
ポイントは、この認定制度の中枢をになう判断をマンション管理士が行うという点です。これが独占業務なのではないか、と巷で話題になっているわけです。