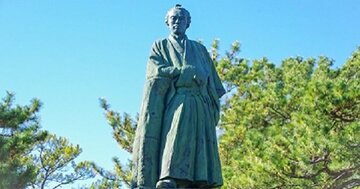一部始終を聞き取った西郷は「解った。宜しい」とだけ言葉を発し、大きく頷いたという。重三が西郷に面会を請うた際の書面には、西郷を「実に社稷(国家)柱石の功臣」とし、天下の士が敬慕していると記している。その西郷に「人倫」に関する危迫(切迫)した願いがあり、哀れみを閣下に求めるのみと重三は書いていたのである。西郷と面会後、重三は執事の「長田様」に宛てて、礼状を書いている。
筆者は、重三の嘆願に心を動かされた西郷が、減免に貢献したと考えたい(これは筆者の推測になるが、西郷が司法卿=現在の法務大臣である江藤に何らかの働きかけをした可能性もあろう)。
 『仇討ちはいかに禁止されたか? 「日本最後の仇討ち」の実像』(星海社新書)
『仇討ちはいかに禁止されたか? 「日本最後の仇討ち」の実像』(星海社新書)濱田浩一郎 著
明治6年(1873年)2月7日、明治政府は仇討ち禁止令を布告する。この禁止令の布告は、高野の仇討ち事件が契機となったとされている。
仇討ち禁止令の内容を見てみよう。「人を殺すのは国家の大禁であり、人を殺す者を罰するのは、政府の公権である。が、古来より、父母のために復讐するをもって義務とする古習が存在している。それは至情(人情)によるものとは言え、結局、私憤をもって、大禁を破り、公権を犯す者であり、罪を免れぬ。それのみならず、理の当否を顧みず、復讐の名義を挟み、濫りに人を害する事件も多い。よって、復讐を厳禁とする。今後、不幸にも親を殺された者は、事実を明らかにして、訴え出よ。もし、そうしたことをせず、旧習に倣い、殺害したならば、相当の罪科に処する。心得違いするな」というのが仇討ち禁止令の中身である。
この法律により、仇討ちは禁止され、近親者を殺害された者は、官憲に訴え出ることとされた。国家が法に基付いて、被害者に代わり、加害者を処罰することが定められたのである。以降、仇討ちは至情の発露や美風ではなく、法律的には単なる殺人となっていくのであった。