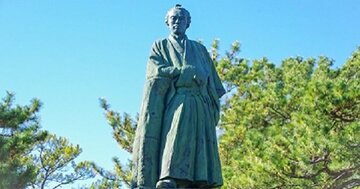今回、真輔は罪がなかったことが明らかになり、仇敵は紀州高野山に登ることが判明した。最早、彼らを捨て置くことはできず、断然復讐に及んだ。「御大典」(法律)を犯したことは幾重にも恐縮しているが、情義によって、復讐に及んだ。決して私怨の行為ではない。以上のような内容が、訴状には述べられている。
「孝行による立派な復讐と認める」
下手人をベタ褒めした五條県知事
赤穂県庁には、五條県から仇討ち一件の通知が来たので、重役等は評議の末、青山直枝を五條県に派遣することになった。直枝が五條に着いたのは、3月14日のことである。直枝は、五條県の鷲尾知事に村上兄弟ら下手人一同の赤穂への引き渡しを要求した。
だが、鷲尾知事は「当庁では、この事件の取り調べを終え、彼らは普通の殺人犯とは違い、孝道(親を敬い仕える道。孝行の道)より出た立派な復讐と認め、検視の顛末書、復讐者の訴状に現場の絵図面を添え、意見を附して台閣に報告し何分の指揮を仰ぐことに手続中であるから、貴藩の申し出には応じられぬ」と赤穂県の要請を撥ね除けたのであった。
赤穂県の重役としては、村上兄弟らが他県で取り調べを受けることにより、赤穂県(藩)への嫌疑を申し立てかねないと危惧し、その身柄を引き取ろうとしたのだろう。が、その企ては失敗した。
村上兄弟らの取り調べは、明治5年(1872年)8月に終了した。判決は死罪であった。
村上兄弟らの行為は復讐とは認められず、謀殺(殺人)だとされたのである。山下鋭三郎ら6名の者は、村上真輔を殺害したことに相違ないが「朝廷寛典の御趣意」によって、既に双方無罪となっている。以後、仇としないという誓書まで提出しておきながら、なお遺恨を持ち、山下らを殺害したことは復讐の律で断ずることはできない。「謀殺の本条」に照らし裁くべきだとされたのである。
明治3年(1870年)2月に制定された『新律綱領』(明治政府のもとでの最初の刑法典)巻3の人命律上には「謀殺」の条があり、そこには「人を謀殺するに造意者(首謀者)は斬」(斬首刑)、「従にして加功する者は絞」(絞首刑)と記されている。