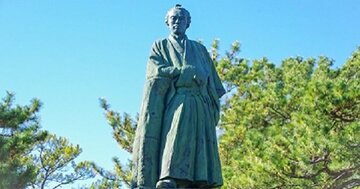急転直下、罪一等を減じ
死罪を免ぜられる
大阪裁判所の早川大判事は、判決文に関連書類を添えて、司法省に上申した。そして司法省は、最後の裁決を太政官に上申する。太政官では、数回の審議が行われ、明治6年(1873年)2月7日、司法省に次のように通達した。
「別紙7名の者断刑、伺之通、死刑に処さるべく処、特命を以て、死一等を減ぜられ候條、此旨、相達すべき事」(『司法省日誌』)。
村上兄弟ら7名は、太政官の最終決定により、死罪を免じられたのである。
死罪が急転直下、減免されたのはなぜであろうか。明治4年(1871年)9月、村上真輔の女婿である神吉良輔の子・重三(24歳)は、参議(左右大臣に次ぐ役職)・西郷隆盛の邸内にあった。重三は、赤穂藩の権大参事(東京詰)であったが、同職を辞してからも、東京にいた。彼は、明治政府の大官に面会し、村上兄弟らの仇討ちへの理解を求めようとした。
その重三が訪れたのが、薩摩藩士として尊王攘夷運動に奔走し、討幕後は新政府の参議として権威があった隆盛の邸であった。面会を求める重三だが、執事から玄関払いをくらう。めげずに、2度目に訪問した時は、誰かの紹介がなければ面会は難しい旨を告げられた。重三は西郷邸の執事の長田という人に、文久事件と高野の復讐に関する記録、拝謁を願う書を託し、取り次ぎを依頼した。
それでも面会までの道のりは険しかった。7度目の訪問で、執事・長田は心を動かされたのか、ついに、重三のことを西郷に言上する。重三は、西郷と対面し「村上一門が期待する所は、命を惜んで酌量減刑を請うものではない。壬戌事変(文久事件)当時に遡り、免れて恥を知らぬ姦魁を糾弾して、公明正大なる御裁判を下されたい。さすれば村上兄弟は喜んで天下の刑典に服する。そうでなければ、国家に刑律なきものとして、やむを得ず一族一門、死を決して第二の復讐を行う覚悟である」と悲憤の涙に咽びつつ、嘆願したのであった。