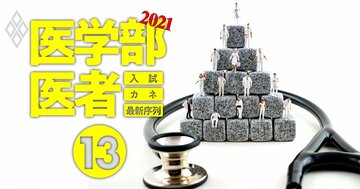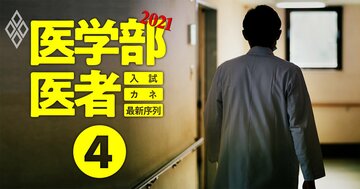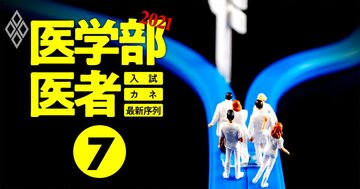小児外科外来の奥にある医師室にたまたまぼくがいた。アポ無し、受付け無しである。言っては大変失礼かもしれないが、父親はかなりくたびれた服装をしていて、顔もやつれていた。ぼくはさすがに可哀想と思い、受け付け無し(つまり無料)で1時間くらい話をした。残念ながらぼくが説明したことは、これ以上の治療は世界中どこにもないということだった。
自分が出した意見は正しかったのか
セカンドオピニオンを求める意義は
さて、これまでにぼくは、何人の患者にセカンドオピニオンを行ったのだろうか。5人くらいだろうか。院長室のパソコンの中をよく調べてみたら20人くらいの家族と話をしていた。そんなに多かったのか。ちょっと、びっくりである。
セカンドオピニオンはかなり骨が折れる。患者家族の話をよく聞き、相手病院の資料を読み込み、自分の意見を家族に伝える。それで終わりではない。向こうの病院の先生に長文の手紙を書いて自分の意見を縷々(るる)述べる。いま、そういう返信の文章を読み返してみると、かなり専門的なことが書かれていて我ながら驚く。
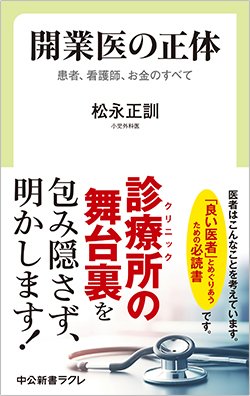 『開業医の正体 患者、看護師、お金のすべて』(中公新書ラクレ)
『開業医の正体 患者、看護師、お金のすべて』(中公新書ラクレ)松永正訓 著
抗がん剤○○は、がん細胞が薬剤抵抗性を獲得しているので、もう中止にした方がいい。代わりに抗がん剤××を4週間隔で○○ミリグラム投与してはどうか……などと実に具体的なことを助言している。開業して最初の数年はぼくもまだ小児がんについて「現役」だったのだなと感じる。
では、ぼくがセカンドオピニオンを述べて、向こうの医者が考え方を変えたかというと、全例でぼくの意見が通った。抗がん剤の使い方が変更になったこともあるし、手術のやり方が根本的に変更になったこともあった。1番目の意見と2番目の意見のどちらが正しいかは神様しか分からないと思うが、患者家族も、1番目の医者も、ぼくの意見に納得してくれたのだから、正しい、正しくないは断言できないものの、悩んでいる患者家族の役には立てたと思っている。