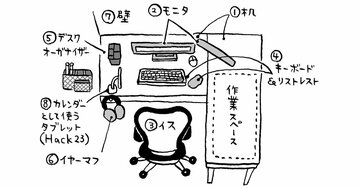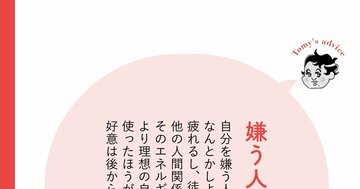写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
恐怖、不安の感情は、原始の時代において生き残る上で重要な役割を果たした。そして、恐怖を学習することによって私たちの先祖は賢く生存してきたのだという。本稿は、原井宏明・松浦文香『「不安症」でもだいじょうぶ ―不安にならない、なくすという目標は間違いです』(さくら舎)の一部を抜粋・編集したものです。
パニック症の根本には
闘争・逃走の本能がある
パニック症や限局性恐怖症の根本には「恐怖反応」があります。恐怖の本来の役割は、自己防衛です。このことは、原始時代を考えるとわかりやすいと思います。
大昔の人間にとって、恐怖は生き残るうえで重要な役割を果たしていました。危険が迫っているときに恐怖を感じると、命を落とす前に逃げたり戦ったりする準備をすることができました。
肉食動物などの捕食者に狙われたときは恐怖反応が出ます。これは「闘争・逃走反応」とも呼ばれ、心臓がドキドキしたり、呼吸が荒くなったり、手のひらに汗をかいたりなど、体は緊張・興奮状態になります。これらはおもに自律神経、とくに交感神経の働きによるものです。
心肺機能が高まるのは、闘うにしても逃げるにしても、血流を一気に上げて手足の筋肉に素早くエネルギーを送り込むためです。手のひらに汗をかくのは、木に登ったり武器をつかんだりするときに滑らないよう手を湿らせておくためです。
また、このときに頭の中では、どうすれば目の前の危険から逃れられるのか、つまり闘うのかそれとも逃げるのか、ということに集中しています。神経が研ぎすまされた状態にあり、ちょっとしたことにも敏感になります。
そして、心身のエネルギーを十分に使って危機を乗り切り、安全を確保できると「闘争か逃走か」モードは解除されます。
このようなメカニズムは、ほかの生物を見てみるとわかりやすいでしょう。ライオン(捕食者)に狙われたシマウマはまずフリーズ状態(凍結反応)になります。草むらで息をひそめていれば、捕食者に気づかれずにやり過ごせることがあるためです。これでは逃げられないとわかったら、シマウマは全速力で逃げ出します。
このように、私たちが不安と呼んでいる恐怖や嫌悪感は生物にもともと備わっている自然な反応であり、私たちが危険を回避し安全を確保するため、遠い祖先から受け継いできた生存に不可欠なものです。
原始時代に比べるとはるかに安心・安全になった現代であっても、暗い夜道を一人で歩くときに体を緊張させておくことで、万が一のときにその場からすぐさま逃げられるようになります。