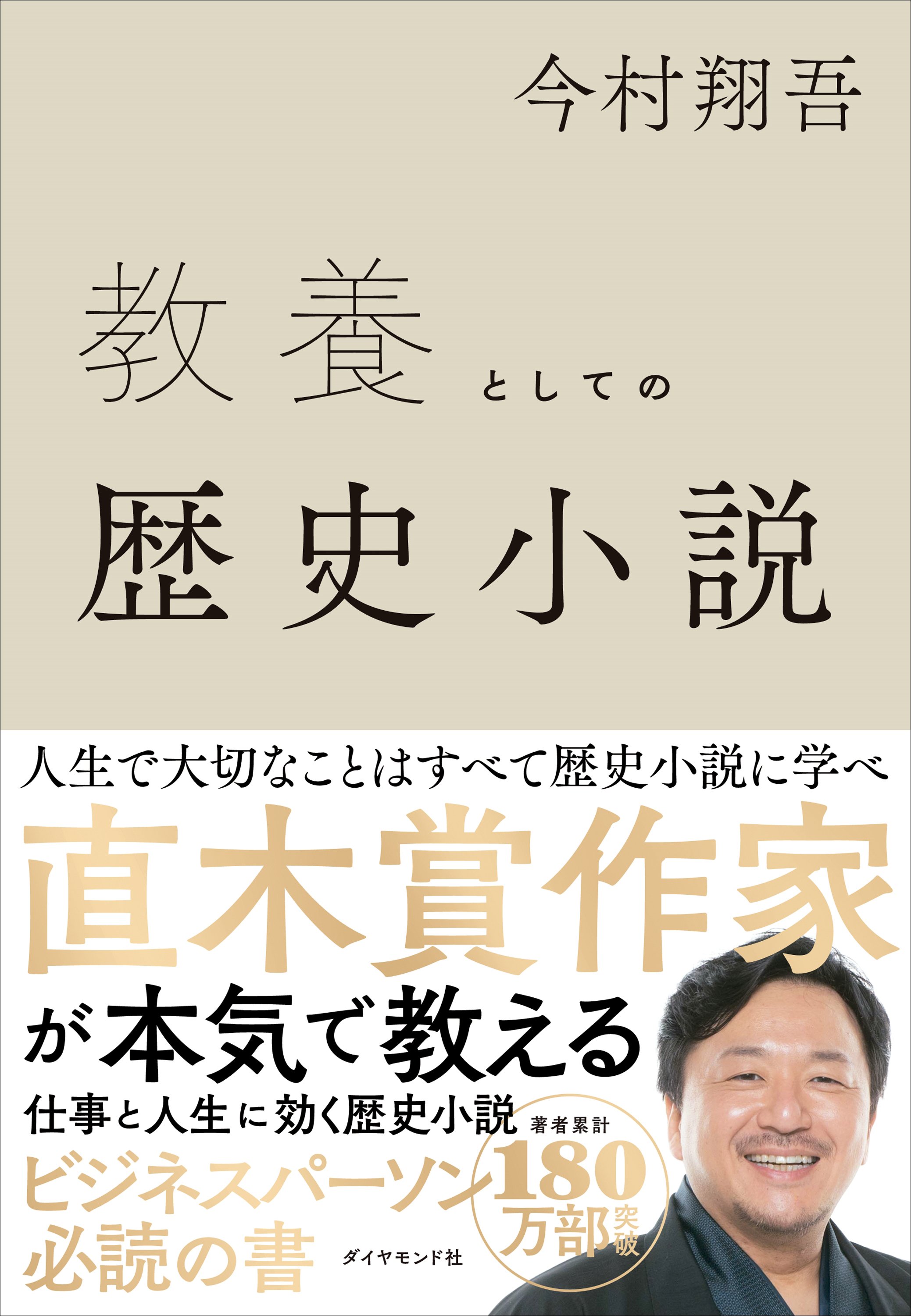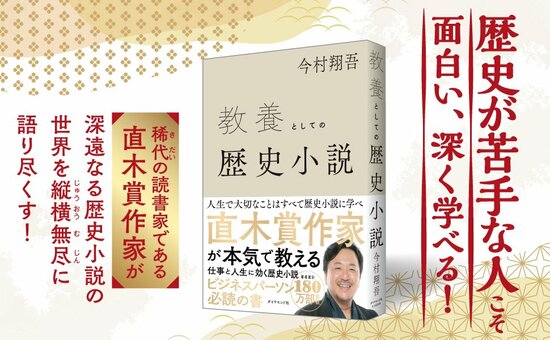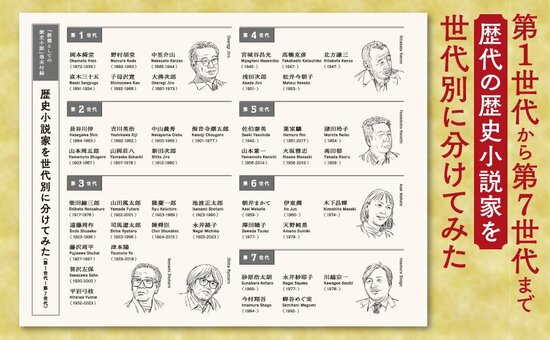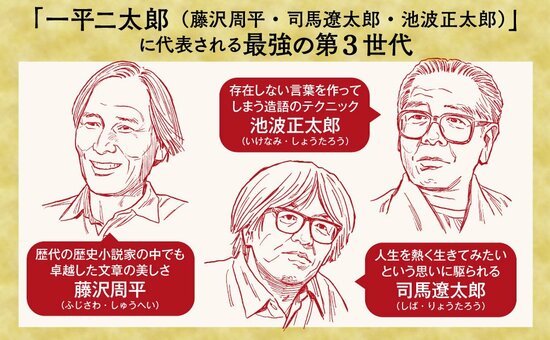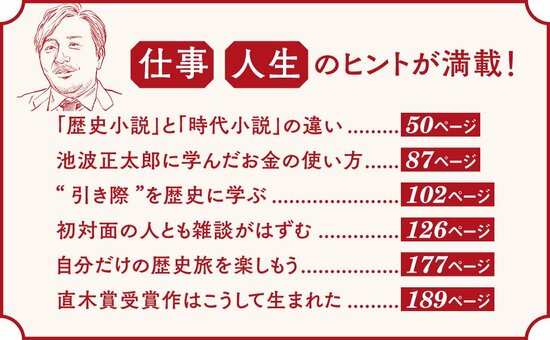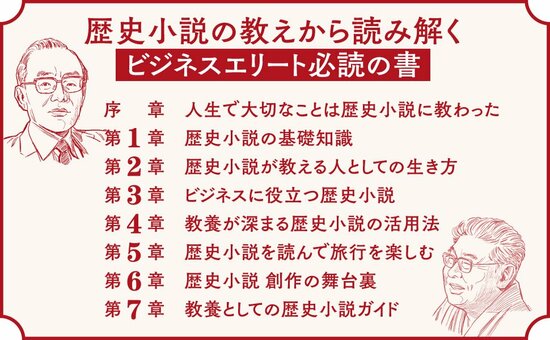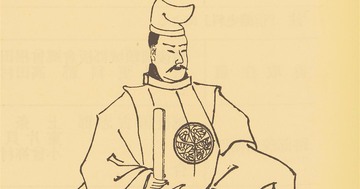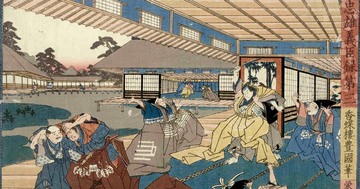直木賞作家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語っている。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、“歴史小説マニア”の視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。
※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
歴史が好きになれば
得意になる教科
すべての学問はつながっています。一つの学問を追究していくと、必然的に他の学問の追究へとつながります。
そして歴史学は、このつながりが起きやすい学問分野といえます。歴史が好きになれば、地理も得意になります。
また、NHKの人気街歩き番組『ブラタモリ』を見ていると、地質学や鉱物学といった地学系の話題が頻繁に出てきますが、それが土地の歴史と不可分に結びついていることがよくわかります。
地学だけでなく
天文学にも結びつき
そのせいか、私も学生時代は地学を非常に得意としていました。天文学も好きで、北斗七星を構成する星も破軍、廉貞、文曲……などと中国名で記憶していました。
一方で、当時は物理と化学にはあまり興味を持てず、熱心に学ぼうと思えませんでした。
ところが、小説家になってからというもの、遅ればせながら化学が少し得意になってきました。
火災の起こり方に
化学反応を調べる
きっかけは『羽州ぼろ鳶組』を書き始めたことです。この作品は江戸期の火消組の活躍を描くので、必然的に作中で火災の起こり方にも言及します。
出火のパターンを調べていくにあたり、化学反応についての知識も少しずつ増えてきました。
出火につながる化学反応は何百パターンもあるのですが、江戸時代に生成可能な物質であるかどうかも調べる必要があります。
歴史を通じて
意外な学びが広がる
そこで硫黄の歴史や火薬の歴史にも、どんどん詳しくなっていきます。
「学生時代に苦手だった科目でも、大人になってからこんなに学びを深められるんだ」というのは、自分にとって大きな発見でした。
生物学にも、ずいぶん詳しくなりました。たとえば、私たちが日常的に食べているトマトは、もともと観賞用として17世紀の日本に伝わってきたものです。
ハイビスカスの
興味深い歴史も
あるいは、観賞用の花として知られるハイビスカスは、日本では「菩薩花」と呼ばれていました。
ハワイの州花であることからわかるように、世界の熱帯、亜熱帯、温帯地方に分布する花でもあります。
日本の本州では栽培が難しく、火鉢で温めながら育てていたので、お金がかかりすぎると文句を言われていたそうです。
教養は深みを増す
これらも、歴史小説を読んだり書いたりする中で身につけた雑学です。
さらに、歴史は数学にも通じています。私が小説を書くときには、電卓を叩いて計算することが、けっこうあります。石高ごとの兵数などを計算する必要があるのです。
『塞王の楯』を執筆したときは、大砲の砲撃の角度を計算する必要に迫られ、編集者と一緒にsin(サイン)・cos(コサイン)を使いながら、図を使って計算しました。
このように、歴史から他の学問へと学びを広げていけば、教養は深みを増します。まさに学びに終わりなしです。
※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。