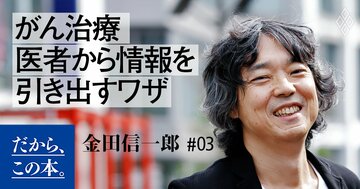マッキンタイアを読みながら、昔見た映画『フェーム』を思い出した。『フェーム』はニューヨークの演劇学校をモデルに、演劇と音楽の専門校に通う学生たちの青春を描いた映画である。そのなかでダンスをあきらめて学校を去るように、教師が一人の学生に痛烈に言い渡す場面がある。このダンス教室にあなたの場所はない、あなたの人生を台無しにするわけにはいかないから、率直に言わなければならない、と教師は言い放つ。
泣きながら教室を去る学生を見送って、それまでの毅然として冷徹だった教師が、苦渋に満ちた顔でため息をつく。その表情が印象的だった。専門教育に携わる教員ならば、多かれ少なかれ経験しなければならない、苦い思いだ。ハーストハウスもマッキンタイアも、おそらく何度も経験したにちがいない。
「真実を医者が患者に告げたからといって、その医者を不親切で非情だとは誰も思わない」かどうか、少なくとも日本では疑問である。それにもかかわらず、ハーストハウスの主張は正しいのではないか。
悔いなき人生を過ごさせるために
真実を本人に隠してはいけない
 『つなわたりの倫理学 相対主義と普遍主義を超えて』(村松 聡、KADOKAWA)
『つなわたりの倫理学 相対主義と普遍主義を超えて』(村松 聡、KADOKAWA)
真実の伝達が友人をひどく傷つけるならば、私たちは言うべき時と所を考えると述べたが、それは真実を告げないことを意味はしない。いつ言うべきか、おそらく友人が耳を傾ける余裕があるとき、必要なときを考える。一方、6カ月の余命しかない患者にとって、告げるときは今しかない。患者が人生の終わりをどのように過ごすか、患者自身が考える最も重要な情報である。本人の人生の決断に必要な真実を本人に隠してはならない。
しかし日本の社会ではそう簡単に決められない、と現場の医師から応えが返ってくるかもしれない。告知に際しては、多くの場合まず家族に相談して、その上で本人に告げている。決定は本人ではなく、家族への相談と共に始まる。こうした社会では欧米と精神的風土が異なるから、同一に論じられない、そう言われるだろう。