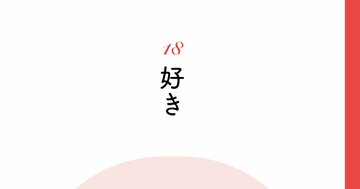写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
こだわり=偏愛を理解することは、根底にある衝動に気づく近道だ。一般的な好みから一歩進み、自分が何を本当に欲しているのかを具体的に言語化し解釈することで、自分にフィットする場所を模索するための新たな視点が得られるはずだ。本稿は、谷川嘉浩『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』(筑摩書房)の一部を抜粋・編集したものです。
FFのフィギュアとレゴの城で
「二次創作」にハマっていた少年
偏愛を掘り下げる上で大切なのは、「小説が好き」「洋楽が好き」「料理が好き」「走るのが好き」くらいのよく使う雑な一般論を避けながら、もっと解像度高く偏愛の性質を理解することです。
具体的には、偏愛している活動に携わっているとき、実際のところ、自分は何を楽しんでいるのかを言語化する必要があります。森の中でちらちらと見える鳥の羽ばたきから鳥の種類や様子を察し、生態について理解を深めることと、鳥の鳴き声によって鳥の置かれている状況や発声の意図を知ることが全く違う活動であるように、低い解像度での偏愛理解は、誤解につながるからです。
そうしたことに気をつけながら、何とか首尾よく偏愛を細かく詳しく語ることができたら、その先には「解釈」という作業が待っています。「解釈」は、言語化した内容をほどほどに一般化し、衝動を言い当てることを指します。
偏愛の解釈について、私の子ども時代を例に説明してみましょう。コカコーラのおまけでついてきたゲーム「ファイナルファンタジーIX」のフィギュアや、他のコンテンツのグッズ、そして、城のレゴブロックを使って、自分の中だけのストーリーを作り出すことに、かつての私は夢中になっていました。これが、私の抱えていた偏愛の一つです。
この遊びにおいて、あるキャラクターが許容しそうな行動かどうかという制約は意識していますが、元のストーリーや世界観は重要ではありませんでした。私が惹かれていたのは、キャラクターとその組み合わせが提案してくる複数の行動可能性と、その都度用意したストーリーの初期設定を即興的に掛け合わせながら、整合的な時間の流れを作って何らかの終点へと向かおうと努めることです。
少年時代の衝動がいまの
研究生活につながっている
要するに、〈異なる分野の題材を組み合わせて、破綻しない形で予期せぬ結末を作ろうとするストーリーテリング〉への衝動を、私は持っていました。ストーリーテリングによって、思いもしない途中経過やエンディングを経験することができることの楽しさに夢中になっていたわけです。ここまで抽象化すればわかると思うのですが、これは現在の私が執筆や研究を通して得ている楽しさと本質的には同じものです。