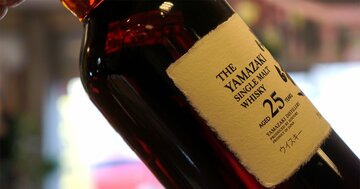興味があっただけではなく、氏はこの本に相当肩入れするところがあったらしく、「まえがき」には「若い知人のA氏は、本書の原書を電車の中で読んでいて、涙が出て困った、という」と書いてあり、また巻末の「あとがき」には「ともかく、人間を感じさせる本であった。その人間くささが、わたしたちに訴えかけ、ほろりとさせた」と書いてある。
で、ほう、それほど感動的な話なのか、と、私も楽しみに読み始めたのだが……、実際に読んでみたら、そうでもなかったです(爆!)。
……っていうか、むしろウザい(爆!爆!)。
結局のところ、創業者社長の父親から見ると、色々な意味で2代目は不甲斐ないのであろう。不甲斐ないし、危なっかしい。そんな時、普通の親子関係だったら、親父が息子にガミガミどやしつけて、しばらくは口もきかない仲になるというあたりが相場。父子関係というのは大概そういうものであって、父子喧嘩を繰り返しながら、それでもその息子が多少なりともまともな奴だったら、少しは父親のアドバイスも受け入れて、いつしか一端(いっぱし)の2代目になると。
息子に意見したいことを
うだうだと綴る粘着質な父親
ところがこの本の父親、つまり著者のウォード氏は、世の一般の父親と比べるともう少し粘着質の男だったようで、息子に向かって意見したいことをうだうだと文章に綴り、手紙として渡していた。
だから、その手紙の内容となると、ねちねちと息子の欠点をあげつらい、その上で「こういう風にしろ」と命令するタイプの父親のそれである。無論、オブラートに包んではあるので、人によっては「ユーモアたっぷりに」と受け取るだろうけれども、そういうことならむしろズバッと直截的に言ってもらいたいと思う私のような人間からすれば、「ウザい」としか言いようがない。
たとえば、同年代の友人たちが次々と結婚し出したのを見て、そろそろ自分もと妻探しを始めた息子の動向を聞き付けたウォード氏は、
《それからその後一生添い遂げることを考えれば、美人を選んだ方が得だ。とはいえ、あらゆる側面でパーフェクトな女なんていないから、ある程度のところで妥協しろ。口説き落とす女が決まったら、用意周到で行け」》