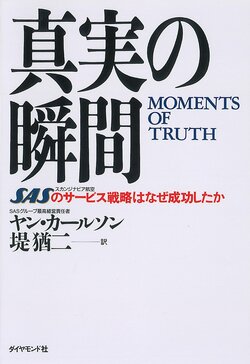顧客と最前線で接する最初の15秒の接客態度“真実の瞬間”が、その企業全体の印象を決めてしまう。この“真実の瞬間”という言葉を広めたのが『真実の瞬間 SASのサービス戦略はなぜ成功したか』という書籍だ。スカンジナビア航空の業績を急回復させた著者のメソッドや思考がぎっしり詰まっている。今回は、サービススキルに関してだけではなく、戦略・マネジメントなど、まさに経営全般について書かれたこの1冊から読者に有益な情報をお伝えしていく。(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
安全な道しか選ばない人は、谷の向こうに渡れない
刊行は1990年。約35年も前の本だが、書かれた内容はまったく古さを感じさせない。
企業が抱えている課題が、実はほとんど変わっていないのではないか、とすら思える。そして企業が変わっていくということがいかに難しいか、ということも教えてくれる。
著者のヤン・カールソンは、1979年から2年連続で巨額の赤字を計上していたスカンジナビア航空の社長に就任。
わずか1年で黒字経営を達成し、専門誌によって年間最優秀航空会社に輝くなど、再建に成功した経営者だ。
彼がスカンジナビア航空の再建のために取り組んだ戦略は、シンプルなものだった。それは、顧客本位の企業に生まれ変わること。
その象徴こそ、顧客と最前線で接する最初の15秒の接客態度“真実の瞬間”だった。それこそが、企業の成功を左右する。
世界の経営者やビジネスパーソンを、まさにハッとさせ、本書は世界中から注目される1冊になった。
だが、それは最前線の現場が頑張ればいい、を意味しない。リーダーこそ、そのくらい大胆な発想転換をせよ、勇気を持って挑戦せよ、というメッセージだと感じる。
同じように、従業員にも企業にも、あえてリスクにいどむ勇気が必要である。ビジネスの世界ではそうした跳躍を強制執行と呼ぶ。明確な戦略があれば、それだけ強制執行は容易になる。この時に問われるのは、向うみずに近い勇気と直観力である。(P.106)
そして、勇気や直観力は習得できるものではないが、素質があれば伸ばすことができる、と著者は記す。
分析は細かくやるのではなく、経営戦略全体を対象に行うべき
何か新しい取り組みを始めようとするときは、それが果たして新しい収益をもたらすかどうか、わからない。
しかし、それでも踏み出せるかどうか、で新しい結果が生まれる。踏み出さなければ、何も変わらない。しかし、わからないことをいいことに、踏み出さない理由ばかり探そうとするリーダーがいる。
なんとも思い切った表現だが、こう続くと、たしかにそうかもしれない、とうなづける人も少なくないかもしれない。
分析的思考の重要性は著者も認める。しかし、分析は細かくやるのではなく、経営戦略全体を対象に行うべきだと記す。
著者は年間赤字額が2000万ドルに及んでいたときに改善費用5000万ドルを追加支出しているが、このこと自体は無謀に見える。
もし、改善事項が経営戦略全体の一環をなすものでなかったとしたら、そうだったかもしれない。だが、経営環境全体を分析した結果、5000万ドルの追加支出を決めたのだ。
思い切った挑戦で、リスクにいどまなければ、大きな成果を挙げることは難しい。
そんなことができるはずがない。失敗したらどうするんだ。認可が下りないだろう。
成功の見込みがない、などと決めつけていたら、アイデアの芽はどんどん摘まれていくのだ。
顧客が求めていることを、業務目標にできるか
そして当然、現場で働く従業員のモチベーションを高めなければいけない。“真実の瞬間”には、顧客に感動を与えられるような仕事が求められるのだ。
これは、言われてできるものではない。実際、著者は業績の評価についても見直しをした。
しかも、顧客視点の根本的なところから。それは、反省から始まっていた。
やがて私たちは、貨物輸送量などという顧客のニーズとはまるで無関係な“役員室”目標を基準に業績を評価するのは誤りであることに気づいた。事実、顧客が最も気にしているのは、依託した荷物が正確かつ迅速に仕向け地に着くかどうかなのである。(P.147)
著者らは戦略を見直し、最高の信頼性を誇る航空会社になることを目標に設定する。
もとより、確実な貨物輸送ができていると思っていた。貨物部門の担当者の報告によると、貨物輸送遅延率は極めて低かった。
ところが改めて調べてみると、貨物の輸送状況が散々であることがわかった。テストでは、翌月に着く予定の小荷物が4日後に到着していた。
こうして、業務実績を、確実性の面から評価するように方針を変えた。
配送日は守られたか。貨物は所定の便に搭載されたか。貨物搭載機到着から貨物引渡し準備完了までの所要時間はどうだったか。こうした項目を重点的にチェックする評価法とした。
そして評価結果を毎月、公表した。レポートには各貨物ターミナルの実績と目標を比較するグラフが添付され、成績が一目でわかるようにした。
結果、貨物が予定通り到着するようになった。貨物を遅らせる問題箇所も明らかになった。
これが貨物部門の日常業務に大きな影響を与えた。スタッフは、上司の指示を待たずに自発的に業務を遂行するようになった。活力とやる気を取り戻したのだ。
著者はこう記している。「最も実質的な報奨は、自分の仕事に誇りが持てることだ」。
“真実の瞬間”のために、リーダーができることはまだまだたくさんあるのだ。
ブックライター
1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。