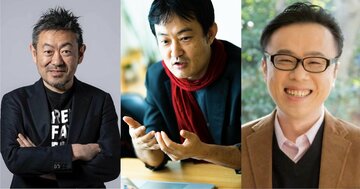算数のプロである小学校や塾の先生ならば「ここで間違えるということは、おそらくこのあたりの単元でつまずいているんだな」と、おおよその見立てができます。
保護者や子ども自身では、それがわからないことがほとんど。そのため、問題を解く「量」で勝負をして、子どもが算数嫌いになってしまうことも少なくありません。
苦手の原因を見つけるために、一度先生に相談してみるのもいいでしょう。
一般的に積み上げの失敗が顕著になるのは高学年からですが、低学年でも積み上げ要素はあります。
たとえば、足し算や引き算など基本的な四則計算は、どのような問題を解く際にも必要です。そのため、低学年でもきちんと練習して習得しておきたい算数の土台だといえるでしょう。
算数への苦手意識は
必ず克服できる
また、「算数の中でも、とくにこの分野が苦手」というケースもあります。
SAPIXの溝端先生は今では算数の先生をしていますが、小学生の頃は図形問題への苦手意識があったそうです。大人になった今、「どうして苦手だったのか?」を振り返ったところ、平面図形の基本パターンをよく知らないまま問題に挑んでいたことが原因だと考えつきました。
当時の溝端先生は、図形問題の得意な子は、問題を見たその場で考えていると思っていましたが、実際はそうではなく、図形の基本パターンをしっかりと頭の中に入れて臨んでいたのです。
平面図形の知識は、立体図形の問題にも応用していく基礎となります。だから、溝端先生は立体図形にも太刀打ちができなかったと語っています。結果、図形全般に苦手意識を抱いていたのでした。
算数への苦手意識があったとしても、それを克服して、算数を教える先生になることもできる。積み上げ教科だからこそ、自分のつまずいている原因を克服すれば、一気に理解が深まることがあるのです。
▼「算数が苦手」と親が言っていると……
(1)本当はできていても、苦手になってしまう可能性がある
(2)「算数は苦手だからしょうがない」とあきらめて思考停止してしまう
▼学び直すべき「つまずきポイント」は、プロに相談するのがベスト
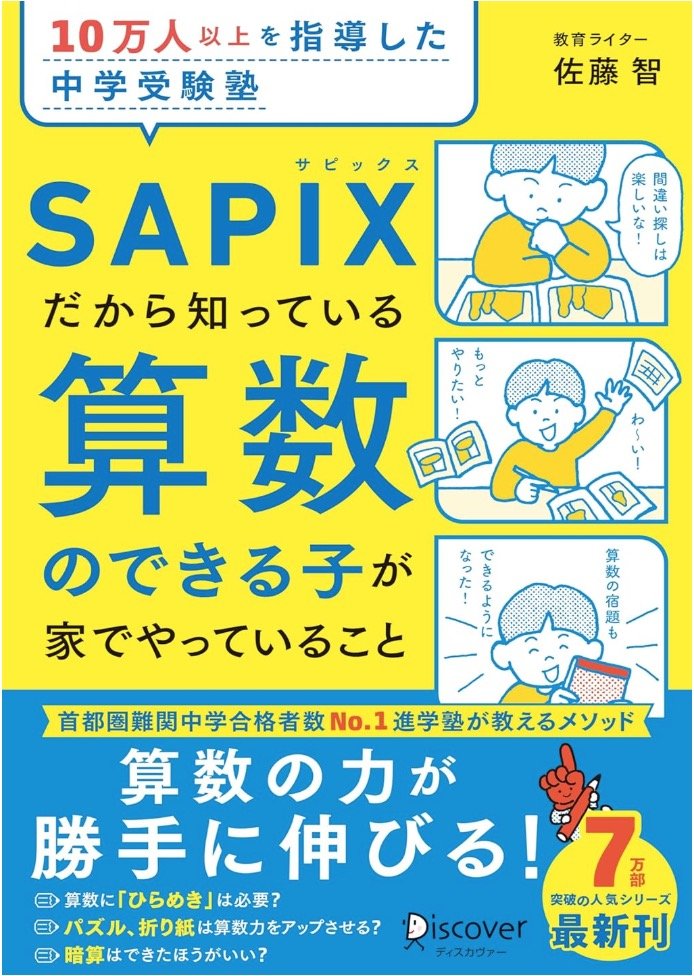 『10万人以上を指導した中学受験塾 SAPIXだから知っている算数のできる子が家でやっていること』(佐藤 智 ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『10万人以上を指導した中学受験塾 SAPIXだから知っている算数のできる子が家でやっていること』(佐藤 智 ディスカヴァー・トゥエンティワン)