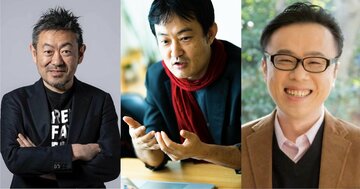家庭でも同じことがいえます。子どもは親の「振る舞い」だけでなく「思考」も真似します。大人は論理的に考えたことを口にだしませんが、「こう考えたんだけれどどうだろう?」と頭の中を少しだけ子どもに共有するのもいいかもしれません。
▼思考力は、瞬発思考、論理思考、自由思考などが組み合わさったもの
▼集団の中で学ぶことで、算数の問題を解く思考法を真似して体得する
「うちの子は算数が苦手」と
安易に決めつけてはダメ
人は一度嫌いになってしまうと、その抵抗感を取りのぞくことは大変です。
これは算数に限った話ではありませんが、勉強は嫌いにさせないことが最大のポイントになります。
そもそも小学生の苦手は、そのあといくらでも変動するものですから、安易に「苦手」という言葉は使わないほうがいいでしょう。
SAPIXでも、保護者から「うちの子、算数が苦手なんです」という相談をよく受けます。
ただ、保護者の話をよく聞いてみると、他の教科と比べて算数で点数がとれない状況だったり、難易度の高い問題が解けなくて、苦手と決めつけていたりします。
算数が苦手だということが保護者の思い過ごしだとしても、「うちの子は算数が苦手で~」といろいろなところで言い続けていると、子ども自身が「自分は算数が苦手なんだ」と思い込んでしまいます。
その結果、本当に算数が苦手になってしまうケースもあるので言葉選びには注意しましょう。
「苦手」と言ってしまうことで起きるもう1つの懸念点は、掘り下げなくなることです。「算数は苦手だからな」という言葉で、思考停止になってしまうのです。「苦手だからしょうがない」と、真剣に問題と向き合わないのは、もったいないことだと思いませんか。どんな問題だとしても解ければ楽しくなります。
また、苦手には、必ず原因があります。
その原因究明こそが大事です。具体的に「ここがわかっていない」と理解して、苦手を苦手のままにしないことで、算数全般への拒否感は生じにくくなります。
算数のプロである先生なら
子がつまずいている単元がわかる
「算数は積み上げ教科」という言葉を聞いたことはありますか?
この言葉は、大抵「積み上げに失敗したから、算数が苦手になった」という言い方で使われます。しかし、別の側面から見ると、算数は体系立って知識が積み上げられている教科だからこそ、どこでつまずいているかがわかりやすいともいえます。