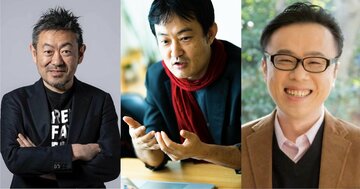写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「数的センス」「図形センス」は経験で育まれる――!? 首都圏難関中学合格者数No.1進学塾のSAPIXの講師いわく、算数を嫌いにさせないためには子どもが算数と最初に出会うタイミングでのアプローチが欠かせないという。「こうすれば楽しく算数を学べる」と子どもに思わせる「算数力が勝手に伸びる」メソッドとは。本稿は、佐藤 智『10万人以上を指導した中学受験塾 SAPIXだから知っている算数のできる子が家でやっていること』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を抜粋・編集したものです。
中学受験で問われる
「瞬発思考」と「論理思考」
最近では、「思考力が大事」とよく耳にするようになりましたが、算数で必要とされる思考力と、一般的にいわれている「思考力」は同じものでしょうか?
SAPIXでも教材を開発する際に「考える」とはどういうことなんだろう、と研究を進めています。
そして、溝端先生(編集部注:SAPIX小学部で長年に渡って算数を担当する小学部事業本部長の溝端宏光氏)は「思考」について次の3種類にわけて考えています。
1 瞬発思考
自分の知識をパッと取りだして答えること。頭の中の引きだしから、必要な知識を探して使う力。
2 論理思考
ある一定の条件の範囲の中で仮説を立てて、答えを導きだす思考力のこと。
3 自由思考
工作などで「空想の生物をつくってください」といわれたときに発揮する力。自分の好みや感性を使う思考力。
現在のテストや入試では、瞬発思考と論理思考が問われることが多いでしょう。中学受験において、自由思考を問われることはレアケースです。
ただ、最近の思考力入試では自由思考が求められる課題も増えました。思考力入試とは、基本的には知識を問わず、子どもが自分で考えて解き方を見つけていく問題が出題されます。また、自由思考は探究学習やアートの領域において大切な力です。
学校や塾で友達と勉強して
「論理思考の使い方」を学ぶ
自由思考は現在の勉強においていかす機会は少ないかもしれませんが、AIが正確性や効率性のある仕事を代替する時代になれば、むしろ「自由思考こそ大事」な時代が訪れるかもしれません。テストで問われないから不要だと考えるのではなく、その子の考える楽しさを大切にしてください。
算数の問題を解く場合には、自由思考がはさまると混乱する可能性があります。
とはいえ、子どもに「ここでは、論理思考を使うんだよ」と伝えても通じません。小学生にとっては、思考方法を説明されるよりも、他の子の考え方を真似るほうがわかりやすいでしょう。
たとえば、1人の練習ではシュートをうまく蹴れない子が、サッカークラブの上手な子を真似することで上達する。または、外国語を学ぶときにその言葉を常用している国に行くと自然に話せるようになる。このように、実体験から学ぶことが重要です。
学校や塾などで友達と勉強することで、「算数の問題に使う思考はこういうもの」と経験させてあげてください。