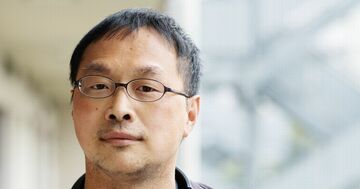日本映画のオーディション不足から、相対的にワークショップに「出会いの場」としての需要が高まり、「監督やプロデューサーと親しくなれば役をもらえるかもしれない」という期待感が醸成されていった。それを隠すことなくビジネス化したのが、俳優など参加者から参加料を取り映画製作を行う、ワークショップ映画だった。
なお、海外のキャスティング事情に詳しい俳優兼言語コーチの川口とも氏によると、アメリカにおいて俳優向けのワークショップを映画監督が担うことはまずないという。さらにアメリカには、俳優への詐欺を防止するためのクレコリアン法があり、様々な規制がなされているという。そのうちのひとつに「ワークショップオーディションとしてのニュアンスがあるなら無料でなければならない」というものがある。
考えてみれば、役に合った役者を見つけることはプロダクションの利益につながることであり、それが有料で俳優側の負担をもって行われていること自体、極めて不自然なことである。残念ながら、日本における俳優ワークショップはクレコリアン法とは真逆の方向に進んでしまった。
日本映画の低予算化がもたらした
ワークショップ映画の隆盛
日本でいくつかのワークショップ団体が続々と映画製作を開始したのが2010年代であるが、そこに至るまでの背景を簡単に書きとめておきたい。
フィルムからデジタルという映画史における大きな時代の変化において、1980年生まれの私はちょうど狭間の世代で、フィルムの映画を見て育ち99年に映画学校に入ったときにはすでにデジタル化が進んでいた。実際、私はこれまでビデオでしか映画を監督したことがない。デジタル化は映画制作に様々な恩恵をもたらしたが、同時に映像業界の低予算化も加速させていくこととなった。
日本映画の歴史について簡単に触れると、1960年代以降に撮影所システムが崩壊し、テレビの普及に伴い映画館の観客動員が急速に落ち込んでいく中で、制作費はジリジリと縮小し、映画会社は新たな戦略を求められるようになった。芸術映画の路線を明確に打ち出した日本アート・シアター・ギルド(ATG)や、一般映画と比べ低予算で利益の上がる成人映画の台頭などがそれに当たる。成人映画路線で代表的なのが日活ロマンポルノ、東映ポルノ、そして大手映画会社以外のプロダクションによるピンク映画である。