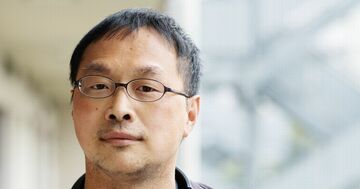その流れは東映Vシネマなどへと引き継がれつつ、時代を経るごとに予算は下降線を辿っていった。1990年代には2000万円程度でVシネマが制作され、「こんな予算じゃ映画なんか作れねえよ」と現場スタッフは毒づいていたと聞くが、2000年以降、デジタル化の浸透によってあっという間に底が抜けた。
2010年から映画会社アートポートがスタートさせた「青春H」というレーベルがあった。文字通り「青春とH」をテーマにすれば何を撮ってもいいという、ピンク映画のソフト版のような触れ込みで始まったシリーズは累計で長編映画42本が作られた。制作予算はなんと100万円以下という超低予算であった。たしかにデジタル化によってフィルム代はかからなくなったかもしれないが、本来であれば長編映画が100万円以下で作れるはずがない。当然、この予算では監督、スタッフ、俳優は十分なギャランティを受け取れないし、むしろ監督の持ち出しになっていたであろう状況は想像に難くない。
「青春H」レーベルの登場により、いよいよ映画の低予算化も行き着くところまで行ったかと思っていたら、底の底がまた抜けて、その後に控えていたのがワークショップ映画だった。
本来ギャラを支払うべき俳優から
お金を徴収するという不自然な手法
ワークショップによる映画制作は、「青春H」シリーズと時期を同じくして盛んになっていった。
その内容は主催団体によって異なるが、プロの映画監督が「講師」となり応募をしてきた俳優やときにスタッフが「生徒」として一緒に映画を作るというものが一般的であった。それはときに「実践的映画教育」と謳われたが、見方を変えれば、本来はギャラを支払うべき俳優やスタッフからお金を徴収して現場に参加させ新作を作るという、安価で映画を作る裏技のような仕組みであった。
そこに教育的意義が一切なかったとまでは言わないが、その作品が劇場で商業公開されていることを思うと、やはり大きな問題を抱えた手法であると言わざるをえない。