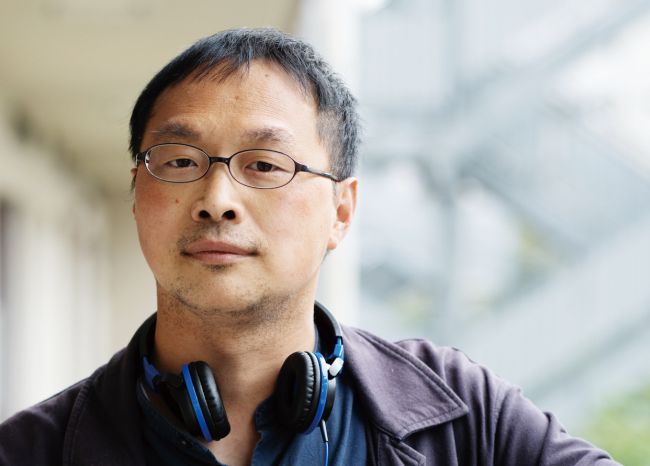 深田晃司監督の作品は、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門を受賞した日本とフランスの合作映画『淵に立つ』(2016)をはじめ、海外でも評価が高い
深田晃司監督の作品は、カンヌ国際映画祭「ある視点」部門を受賞した日本とフランスの合作映画『淵に立つ』(2016)をはじめ、海外でも評価が高い
「アカデミー賞を受賞!」「カンヌ映画祭で受賞!」――。海外での日本映画の“快挙”が華々しく報じられる一方で、近年、これまで表沙汰にならなかった監督の俳優に対する性暴力やミニシアターでのパワハラ、低賃金に長期労働、人手不足、ジェンダー格差など、映画業界のさまざまな問題が可視化され、業界全体の構造見直しが叫ばれている。課題の洗い出しから、具体的な解決法の提示にまで踏み込んだ話題の新書『日本映画の「働き方改革」: 現場からの問題提起』(平凡社)の著者、深田晃司監督は、「日本の映画業界は、安心して親が子どもを送り込める環境ではない」と指摘。映画だけで食べていける監督は「実は一握り」だと言い切る。深田監督が訴える、日本映画の「働き方改革」とは。(取材・文/編集者・ライター 西野谷咲歩)
1年の公開本数は676本
なぜ日本映画の製作本数は多いのか?
現在、何本の日本映画が劇場公開されているかご存じだろうか。
一般社団法人日本映画製作者連盟によると、2023年の公開本数は676本。1日にほぼ2本弱の映画が公開されている計算だ。興行収入は1481億円。うち興行収入10億円以上の作品が34本で、合わせて1139億円。全興行収入の実に8割弱だ。その多くを大手映画会社の作品が占める。なお、東宝、松竹、東映の大手映画会社3社は、製作・配給・興業すべてを担っている。
そもそも676本という製作本数は海外に比べてかなり多いと、深田監督は話す。「前提として、日本はかつて映画大国で、(東宝スタジオ、東映京都撮影所など)撮影所が複数あり、映画を作る文化的土壌があります。撮影スタジオが量産・供給体制を維持していた頃の名残でインディペンデント映画(中小の製作会社もしくは個人資本によるアート性の高い作品)を上映するような映画館、いわゆるミニシアターも諸外国と比べても都市部においてはやや充実している印象です(23年12月末現在:3653スクリーン)」。
さらに、映画を撮りたい監督やプロデューサーが多数存在すること、また日本独自の問題として、「低予算でも映画が撮れてしまうこと」を理由に挙げる。







