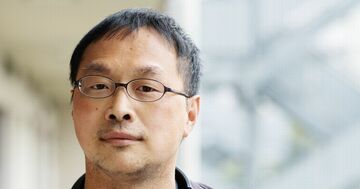音楽や絵画、文学、漫画といった他の表現手法と映画の大きな相違点は、映画は膨大な資金が必要な表現であるという点だ。だから、プロデューサーは相応のリスクを負って資金を準備してから映画を作る。それはアクション映画であろうとアート映画であろうと本質的には同じで、それゆえにどこの国の映画プロデューサーも2年3年と時間をかけて出資を募り助成金に応募し、資金集めに尽力して、スタッフや俳優の人件費を準備し、ようやく映画を作るのだ。それがプロデューサーの仕事であり、そこまでしているからこそ、彼らは作品の権利を手にすることができる。
しかし日本のワークショップ映画の「プロデューサー」は、そのリスクを十分に負っているといえるだろうか。
ワークショップ映画の背後に潜む
権利ビジネス目的のプロデューサーに注意
海外においても、どうしても資金が集まらなかったときに、相互の承諾のうえで俳優がノーギャラで出演するケースはある。しかし、そういった場合においては、監督やプロデューサーはいわば自身の人間関係を作品のために投下し消費する最低限のリスクを負っているといえる。
ワークショップ映画はその最低限のリスクさえも「教育的意義」の美旗のもとに回避し、悪くいえば「どうしても映画を作りたい、どうしても出演したい」関係者の気持ちを利用する、典型的な「やりがいの搾取」である。
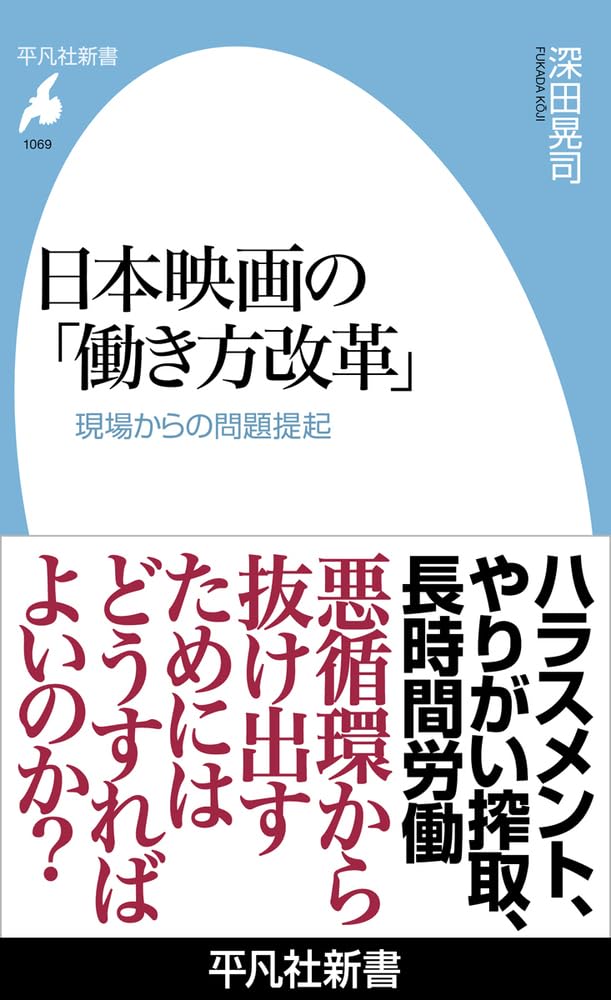 『日本映画の「働き方改革」現場からの問題提起』(深田晃司、平凡社)
『日本映画の「働き方改革」現場からの問題提起』(深田晃司、平凡社)
「貧しくも手弁当で純粋に映画と向き合っている」ことがまるまる美談となってよいのは、せいぜい若手の自主映画までである。ワークショップ映画の背後には、そこで作られた作品の権利を得てビジネスを行う法人なりプロデューサーがいるということを忘れるべきではない。
最後に補足であるが、「青春H」やワークショップで作られた作品の質はここでは問うてはいない。予算があればたしかに質は上がりやすいが、劣悪な撮影現場から傑作が生まれてしまうこともままあることだ。それだけ映画の神様は気まぐれである。それゆえに、作品の「面白さ」によって制作過程における労働問題がうやむやになり、正当化されることがこれまで何度も繰り返されてきた。「作品のクオリティ」と「労働問題」を一度は切り離して考えなければ、搾取の問題を永遠に見失うことになるだろう。
私たちの世代の監督は、