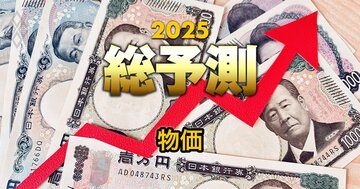家計の消費性向の低下幅(2024年と
23年の比較、総世帯のうち勤労者世帯)
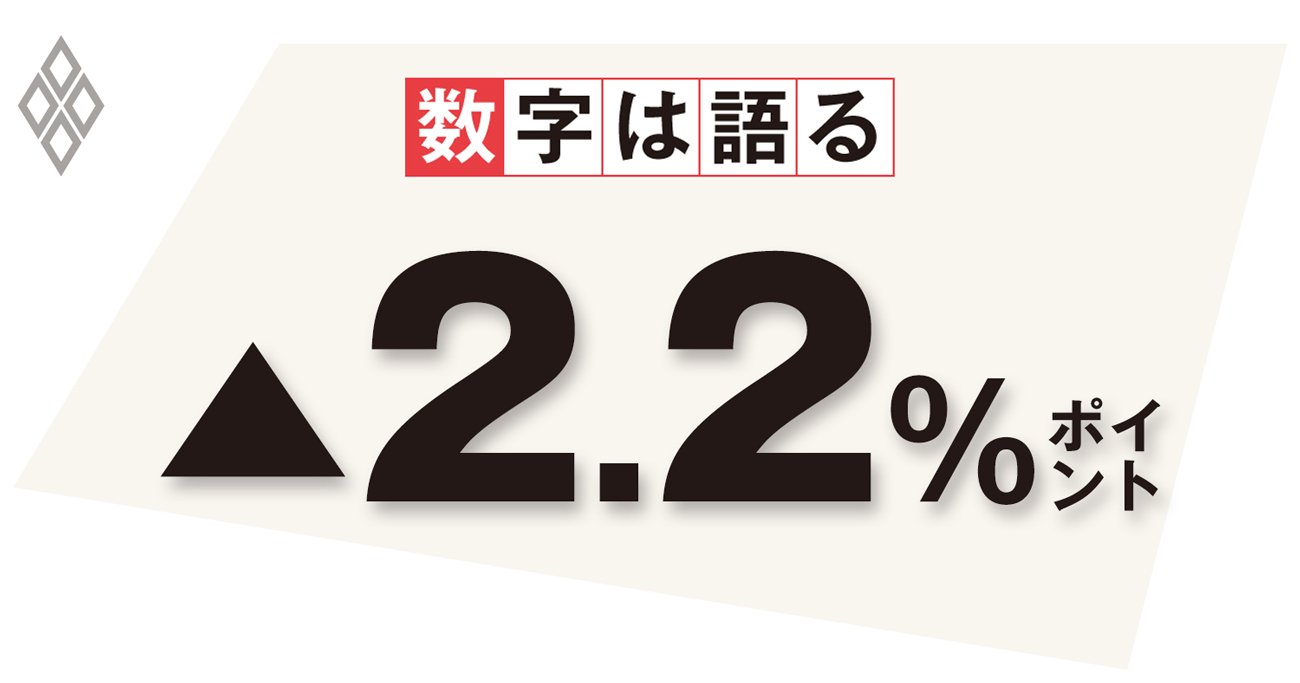 家計の消費性向の低下幅(2024年と23年の比較、総世帯のうち勤労者世帯) *総務省「家計調査」を基に日本総合研究所算出
家計の消費性向の低下幅(2024年と23年の比較、総世帯のうち勤労者世帯) *総務省「家計調査」を基に日本総合研究所算出
個人消費の低迷が続いている。総務省の家計調査によると、2024年の総世帯の実質消費支出は前年比▲1.6%と、23年(同▲2.4%)に続き減少した。名目ベースの消費支出は同+1.5%と増加したものの、大幅な物価上昇によって購入量が伸びず、実質的な消費水準が低下した形である。
実質消費支出の減少を、家計の実質的な所得水準を表す実質可処分所得と、家計が所得のうち消費に回した割合を表す消費性向に分けてみる。すると、23年と24年で消費低迷の主因が変化していることが分かる。
23年は、消費性向が前年比1.0%ポイント上昇したものの、実質可処分所得が同5.7%減少した。大幅な物価上昇に所得の伸びが追い付かず、家計の購買力の低下が消費を下押しした。
24年は、物価の騰勢がやや鈍化する中、企業に賃上げの動きが広がったことによって、実質可処分所得は前年比1.6%増加した。一方、消費性向は同2.2%ポイント低下しており、家計が所得の増加分以上に消費を抑制した姿が見て取れる。物価上昇が長期化する中、賃上げの持続性も不透明なため、家計が節約志向を強めた可能性がある。
このように見ると、個人消費の拡大には、家計が持続的な所得環境の改善に確信を持つ必要があり、25年春闘での賃上げの動向が消費回復の鍵を握る。政府には、物価上昇に伴う負担の一時的な軽減ではなく、企業の成長投資への支援の拡大など、生産性の向上と賃上げの好循環を早期に実現する取り組みが求められる。
消費回復に向けては、持続的な賃上げを実現することに加えて、高齢世帯にも賃上げの恩恵が及ぶように、高齢者の就労環境を整備することも重要である。高齢世帯は、マクロ経済スライドにより年金受給額の伸びが物価上昇未満に抑制されており、現役世代以上に将来の所得増加の展望を描きにくいからだ。
政府は、キャリア開発やリスキリング、企業とのマッチングの支援など、高齢者の就労を促進する取り組みにも注力する必要がある。
(日本総合研究所調査部 副主任研究員 村瀬拓人)