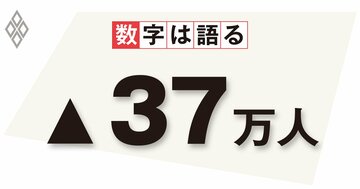村瀬拓人
AIがもたらす生産性の向上、自動化を目的としたAIの利用が、雇用の不安定化を招く懸念も
生成AIの利用が急速に広がる中で、AIが日本経済の生産性や成長率を押し上げるとの期待が高まっている。

低金利依存が続いた日本の財政、本格的に金利が上昇する前に、財政再建の具体的な道筋を示せ
国と地方を合わせた日本の政府債務の残高は、2023年度末で1220兆円に上る。対名目GDP(国内総生産)比で見ると206%と、先進国の中で最悪の水準にある。インフレが定着しつつある中で、財政再建の必要性はかつてないほど高まっている。

集積の経済で広がる東京と地方の生産性格差、高付加価値サービスは東京に集中
東京と地方の労働生産性格差が拡大している。東京都と、その他の道府県の生産性格差は、リーマンショック後にやや縮小したが、10年代半ば以降、再び拡大している。
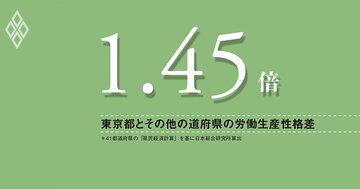
トランプ政権の相互関税で中小製造業の雇用調整が加速、長期化に備えた政策対応を
米国のトランプ政権は、4月初旬に全ての国に対して一律10%の関税を課した上で、国別に追加税率を上乗せする相互関税の導入を発表した。その後、10%を超える上乗せ分には90日間の猶予期間が設けられたものの、この期間内に日米の通商交渉が不調に終われば、日本には合計24%の追加関税が課される可能性がある。
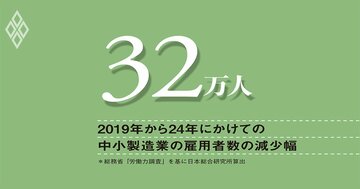
強まる家計の節約志向、個人消費の回復には持続的な賃上げの実現が鍵
個人消費の低迷が続いている。総務省の家計調査によると、2024年の総世帯の実質消費支出は前年比▲1.6%と、23年(同▲2.4%)に続き減少した。

輸出品の品質は向上したが輸出数量は大幅に減少、海外市場への適応が課題に
輸出の低迷が目立っている。日本銀行の「実質輸出入の動向」によると、わが国の財の輸出は、新型コロナウイルスの感染拡大直後に大きく落ち込んだ後、2021年半ばにかけて急速に持ち直した。だが、その後は横ばい圏で推移しており、24年上期の実質輸出は21年上期の水準を2.7%下回ったままである。

未活用の労働指標から分かる労働供給の天井、政府は労働力の拡大を急げ
国内の景気は停滞感が続く中、企業の人手不足に緩和の兆しは見られない。日本経済の先行きは、物価上昇の緩和や個人消費の持ち直しを背景に、景気が回復に転じるとの見方が多い。しかし、その足かせになり得るのが、人手不足という労働供給の制約だ。

2024年は「中堅企業元年」、中小企業と同列に扱う支援制度の拡大に疑問も
政府は2024年を「中堅企業元年」と位置付けた。これまで大企業とひとくくりにされ支援の対象外になることが多かった、中堅企業の成長力の強化に取り組んでいる。

社会保険料の負担増を背景に家計の可処分所得は伸び悩み、中長期的な負担の軽減が急務
足元の日本経済は停滞感が強まっている。とりわけ、個人消費の低迷が顕著だ。民間エコノミストの経済見通しを集計した「ESPフォーキャスト4月調査」によると、1~3月期の個人消費は、4四半期連続の減少が見込まれている。

企業の新規求人「減少」が示す人手不足への対応の変化、設備投資の積極化にシフト
日本経済は深刻な人手不足に直面しているものの、足元の企業の求人意欲は低調である。なぜ企業は足元で採用活動を縮小させていたのか。

人件費や物価の上昇が設備投資の回復の妨げに、利便性の高い投資支援策を
日本経済は回復基調にあるものの、その足取りは緩やかだ。特に足元で停滞感が強いのが、企業の設備投資である。足かせとなっているのが、人件費の増加や物価上昇に伴う投資コストの上昇である。

高所得者層への恩恵が大きい電気・ガス・燃料費の補助金、的を絞った物価高対策を
日本経済はコロナ禍からの回復が進むものの、家計の消費活動は停滞感の強い状況が続いている。こうした中、政府は物価高に対応するための経済対策として、9月末で終了予定だった電気・ガス料金や燃料費(ガソリン・軽油・灯油)抑制のための補助金の延長を検討している。

コロナ禍からの経済活動の回復に伴い、企業が設備投資に積極的だ。とりわけ、設備投資を積極化しているのが中小企業で、コロナ禍で先送りとなっていた既存設備の更新だけでなく、ポストコロナを見据え、人手不足への対応や生産能力の増強といった投資が増えている。

大企業を中心に賃上げ機運が高まっている。連合の2023年春季労使交渉の第2次集計によると、賃上げ率の平均は3.76%と、30年ぶりの高い伸びとなった。今後は、この動きが中小企業にも広がるかどうかが焦点になる。

ウィズコロナを前提とした生活様式への移行が進み、経済活動の回復が本格化している。とりわけ、年末年始にかけては、外食や旅行に出掛ける人だけでなく、入国規制の緩和を受け訪日観光客も着実に増加した。このような旺盛な需要により、飲食業や宿泊業を中心に深刻な人手不足を懸念する声が広がっている。

コロナ禍で労働時間の減少が続いている。厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、労働者1人当たりの労働時間を表す総実労働時間は、新型コロナ流行直後の落ち込みから回復傾向にあるものの、依然としてコロナ前を1.7%下回っている。

企業の設備投資の回復が顕著だ。財務省の法人企業統計調査によると、2022年4~6月期の設備投資(季節調整値)は12.4兆円と、前期比で3.9%増加し、新型コロナウイルス感染拡大直前の20年1~3月期の水準にほぼ回復した。

足元の為替市場では、大幅な円安が進んでいる。年初に115円前後で推移していたドル円レートは、3月以降、急速に円安が進行し、6月22日に136円台など、1998年以来の安値を付けた。かつては日本経済にとってプラスと捉えられていた円安だが、足元では景気への懸念材料として注目を集めている。

ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに資源価格が高騰しており、景気への悪影響が懸念されている。民間エコノミストの予測を集計したESPフォーキャスト4月調査によると、2022年度の経済成長率は+2.4%と、侵攻前の2月調査と比べ0.6%ポイント下方修正された。今後1年以内に景気後退に陥る確率の予測平均も、31.6%に上昇している。

昨年10~12月期の実質GDPが前期比年率+5.4%と高めのプラス成長になるなど、日本経済は昨年末にかけて一時的に持ち直しの動きが見られた。もっとも、雇用環境には依然として厳しさが残っており、同時期の就業者数は、前期に比べ37万人減少した。