「経済成長と環境負荷は比例関係」から
「経済成長と環境負荷は分離可能」へ
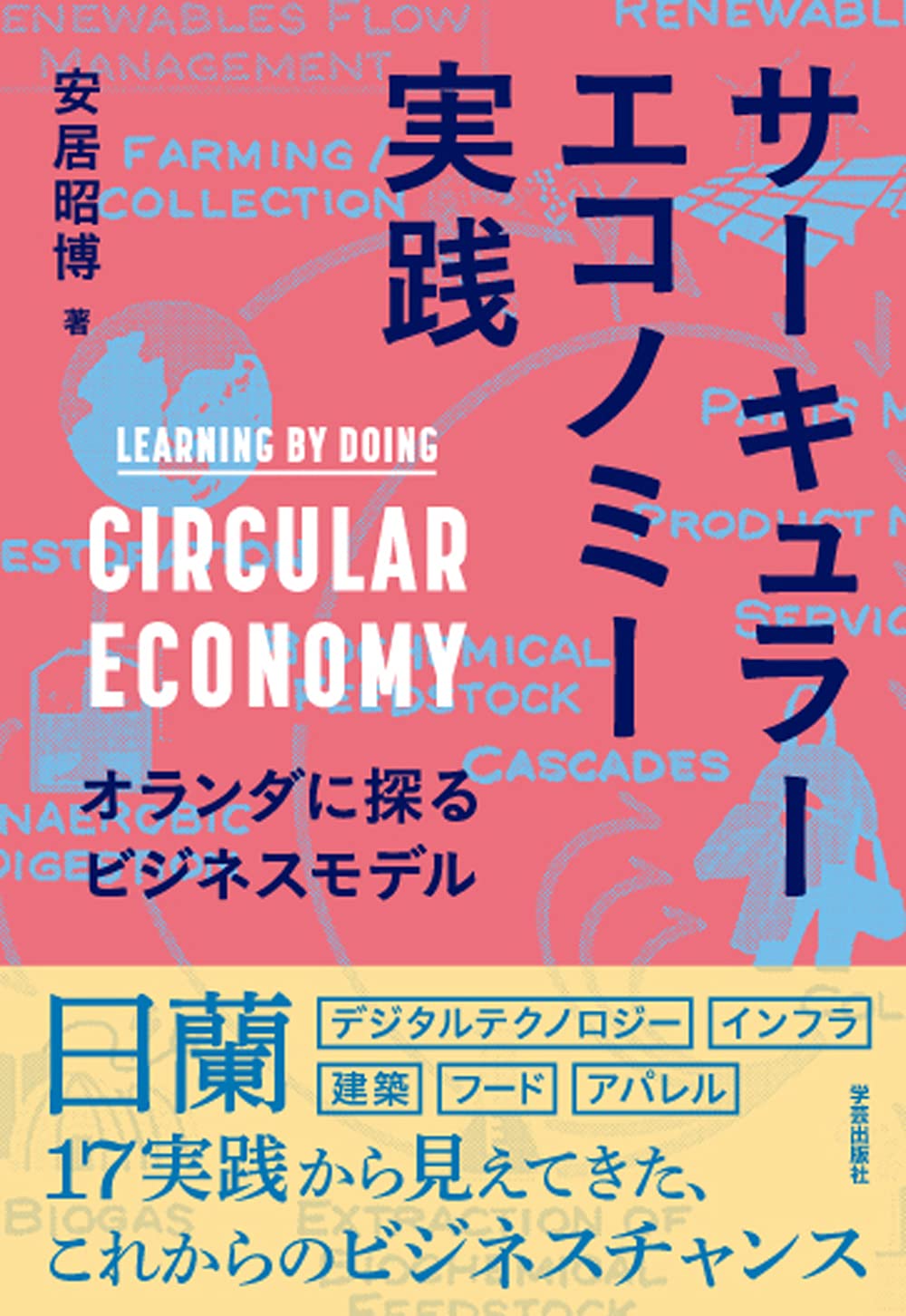 安居昭博『サーキュラーエコノミー実践 オランダに探るビジネスモデル』(学芸出版社)
安居昭博『サーキュラーエコノミー実践 オランダに探るビジネスモデル』(学芸出版社)
大量生産・大量廃棄を前提としていたリニアエコノミーでは、経済成長と環境負荷は比例関係にあり、経済発展を目指すのであれば環境への負荷が拡大しても仕方がないと捉えられていた。
しかし、エレン・マッカーサー財団等の調査によると、企業がサーキュラーエコノミーへの移行を進めることによって経済は右肩上がり(成長)しつつも、環境負荷は右肩下がり(減少)が達成できることが明らかになっている。
例えば、前述のマッド・ジーンズは新しいジーンズの製造に必要なコットンのうち、2021年5月現在で40%は古いジーンズから採取された繊維が使用されているため、新しく調達するコットンの量は従来の60%で済んでいる。また彼らは、100%リサイクル素材から製造するジーンズの研究開発を大学機関と進めており、環境への負荷を年々減らしながらも事業の成長に繋げるモデルを発展させている。
このように、経済成長と環境負荷の分離が実現できることもサーキュラーエコノミーの特徴だ。
GDPはあくまで「短期的利益追求型」であり
長期的な成長予測は論じられない
世界人口の増加、枯渇性資源不足への懸念、廃棄物量の増大といった、もはや無視できない要因を背景に、各国政府と企業の間では従来の前提条件や常識の見直しが進められている。
その中でも大きな変化が、「国内総生産(Gross Domestic Product : GDP)」の偏重を見直す動きである。イギリスの経済学者ケイト・ラワース(Kate Raworth)氏の著書『ドーナツ経済が世界を救う』(河出書房新社、2018)では、GDPの歴史と欠点が分かりやすくまとめられている。
「GDP」とは、「国内で一定期間内に生産されたモノやサービスの付加価値の合計額(※)」であり、戦後から現在に至るまで国の成長の尺度として用いられてきた。本書によれば、GDPの歴史はアメリカの経済学者サイモン・クズネッツ(Simon Smith Kuznets)氏により、世界で初めて、一年間あたりの一国民の所得と、一国の年間所得/生産量が算出された、1930年代にまで遡る。この数字は「国民総生産(Gross National Product : GNP)」と呼ばれ、後にGDPが生まれる基礎となった。
※内閣府「GDPとGNI(GNP)の違いについて」https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/otoiawase/faq/qa14.html(最終閲覧2021/5/28)
「GNP」は、第二次世界大戦終結前後からアメリカ大統領選の公約にも採用されるようになり、あたかもGNPの向上が失業対策や貧困対策、治安改善、教育や社会福祉の充実、国力の増強、そして国民の幸福度向上といった全ての課題改善に繋がる「万能の指標」であるかのような誤った認識が拡大してしまった。
その後、他国の選挙でもGNPをもとにした短期的経済成長がますます重視されるようになり、各国は「GNPランキング」といった形で上下比較されることとなった。結果として、戦後から現在に至るまで世界中の国家や企業のあり方、個人の生き方、そして子どもたちの教育までもが、一国のGNP向上を最優先とする考え方と密接に結びつけられるような構造が生まれたのである。
一方で提唱者であるクズネッツ自身は、GNPを万能の指標のように扱うことは決してなく、「国民が幸福かどうかは、国民所得という尺度からはほとんど推測できない(※)」として、むしろGNPの限界について警告を発していた。
※ケイト・ラワース著、黒輪篤嗣翻訳『ドーナツ経済が世界を救う』(河出書房新社、2018、50頁)
しかし、クズネッツの言葉には耳が貸されないまま政策決定や大統領選が行われ、GNPに代わってGDPが使用されるようになった90年代以降でもあたかも万能の指標かのような解釈が世界中へ広まってしまった。ラワースはGDPが内包する欠点を次のように指摘する(※)。
※ケイト・ラワース著、黒輪篤嗣翻訳『ドーナツ経済が世界を救う』(河出書房新社、2018、281、289頁)
一つが、GDPでは長期的な成長予測が論じられないことだ。
例えば、2100年までの人口増加や地球温暖化、海面上昇に関する予測は公表されているが、2100年までの日本のGDP長期成長予測はできない。また、既に経済発展を遂げた日本やフランスの成長率が現在0・2%前後に留まっているように、長期的に成長が鈍る性質があることも明らかになっている。さらに、GDPでは廃棄物や公害等の外部不経済が考慮されていないことも、見逃せない欠点だ。
このように国策としてGDPが偏重されたことで、企業のビジネスモデルは短期的利益追求型になりがちで長期的視点が蔑ろにされてきた。
「3つのP」を軸にサーキュラーエコノミーへの移行が進められる中、GDPに偏った社会のあり方を見直し、GDPはあくまでも「短期的経済成長」を示す指標としてのみ位置づけ、人々の幸福度や環境、教育の機会、男女格差、平和度、政治的腐敗度、報道の自由度といった社会に欠かせない要素を多角的・包括的に評価する仕組みづくりが進められている。
(第4回へ続く)







