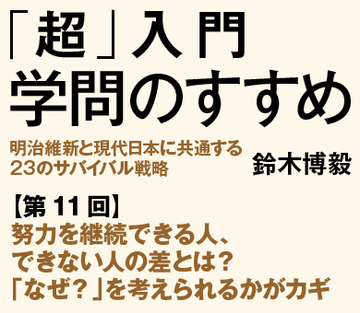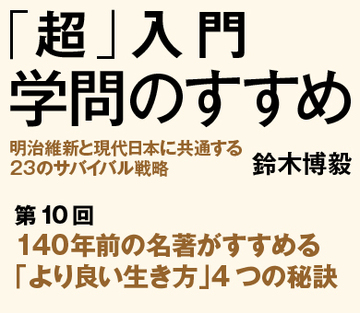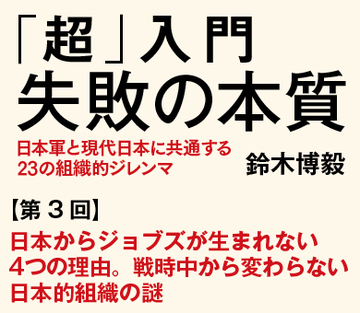福沢諭吉が教える
「接する技術」4つのコツ
諭吉の自伝と『学問のすすめ』から、新たなモノに接する技術を以下4つご紹介します。
(1)きっぱりと古いものを捨てる
長崎留学の際、諭吉は古い中津に一切の郷愁を持ちませんでした。その後、兄が亡くなったとき諭吉は福沢家の当主となりますが、大分県の中津から適塾へ戻り、学問を再開したい故に母親に許しを請い、家財を売り払って大阪に出てしまいます。これぞ!という世界には思い切りよく、果敢に飛び込む人だったのでしょう。
(2)先を行く存在、と手合せする
大阪の適塾から、江戸の中津屋敷の講師をするために上京した諭吉は、文化の中心であった江戸の学者のレベルがどの程度か気になります。そこでわざわざ出かけて行って、江戸の学者にいろいろ質問をします。
諭吉は「大阪から来たのは、学ぶためではなく教えるため」と自負していたのですが、思い込みだけで根拠なく見下しても間違いが起こるので、相手の実力をいろいろ確かめる行動をこっそり起こしていたのです。
新しいものが出現した時、プライドだけ高い人たちは、避けて接することを拒みます。自分が万一彼らよりレベルが低ければ、恥をかいてしまう不安があるからです。
ところが諭吉は、新しいものに接して積極的に「手合せ」をしています。これはアメリカ、欧州に渡った時も同様で、恐れることなくさまざまな質問をして見聞し、新しい存在に好奇心をぶつけました。
手合せをする、とは「武道で試合をする」などの意味でつかわれることが多いのですが、ビジネスマンである私たちにとっては「その相手にまず実際に触れる」ことだと言えます。
そこで「優劣を決める」「相手より自分が上か下か」などと考えると、尻込みしてしまいますが、接触すること自体に価値があると考えると、素早く行動することができます。
福沢諭吉のように、好奇心や理由がプライドに勝る人は、自分を守るよりも相手に接することで、簡単に自分の世界を広げていくことができるのです。
(3)学問は巻物ではない、精神と頭脳を活用する
『学問のすすめ』には、江戸に留学に出てきた地方の書生が長年の苦学の末に、江戸で権威ある学者から学んだ内容を巻物に写して田舎に送ったところ、その船が難破してしまい、自分の学問が全部流れてしまった、と嘆く愚かさを指摘した例えがあります。
新しい情報や学問、知恵や文化に接しても、自らの頭脳と精神の中で活かすことがなければ、偉い先生の言葉をノートに写すことが「学問」だと勘違いした書生を笑えません。
何かに接した時「自分の人生にどう活かせるか」「自分がどう成長できるか」「その知識や体験を何に使えるか」など、主体的な意識を持つことが姿勢なのです。
(4)師は知識や肩書だけではなく、姿勢と人間性を加味する
何かを学ぶとき、師を選ぶとき、単純にその瞬間の知識・技術だけを基準にしていると、相手を間違えることになります。なぜなら、学習を含めた研鑽には「継続性」という別の側面があるからです。
諭吉は長崎に留学した際、松崎という人物からオランダ語の基礎を学びますが、その人物をよく見ることで、単に先に学習をしているだけで、人間性などは大した人物ではないと判断します(この判断は当たります)。
後年、大阪の適塾で諭吉が指導する立場になったとき、この長崎の松崎という人物が適塾で教えを受けにきた際、諭吉は遥かに学問を進歩させており、完全に教える側の立場に逆転していたのです。
技術や知識は一過性でも、その人の姿勢や資質は継続的なものです。「良い接し方」を理解する時、相手の知識だけではなく、人間性までを加味した上で、師とする人物を選ぶことが重要なのです。