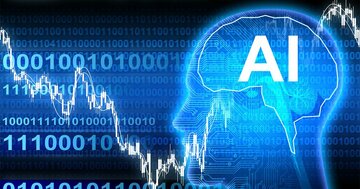ネットで失われつつある
思いがけない本に出会う機会
自分が取り組んでいる研究に関係した論文を「カレント・コンテンツ」(Current Contents。1958年にInstitute for Scientific Information社が刊行した目次速報誌。主題ごとに学術雑誌、会議録、専門書の目次、著者抄録、書誌情報等が掲載されていた)のタイトルの中から探していくなかで、タイトルを順番に読みながら、自分の研究とは直接関係がないのだが、「なんだかおもしろそうだな」という論文に出会うことがある。「犬も歩けば棒に当たる」のようなものである。とはいえ、これは歩いていないとぶつからない。
いまは格段に効率が良くなり、自分の欲しい論文はすぐ手に入る。インターネットでキーワード検索すれば即座に出て、ダウンロードもすぐにできる。便利だが、逆にキーワードに関係しない情報はほとんど入ってこないシステムだ。
これは、私たちが普段読んでいる本についてもいえる。たとえばAmazonは便利で、私も時々使ってしまうが、私の息子は「あれは本屋を潰す」と言って、Amazonを使わず必ず本屋に行っている。たしかに本屋に行くと、背表紙を眺めているだけで思いがけない本があることに気づき、予定になくても買ってしまうことがあるが、ネット書店ではそういうことはほとんど起きない。
是枝裕和さんはいまやもっともよく知られた映画監督だが、彼は昔、私のエッセイ集『もうすぐ夏至だ』(白水社)を本屋で見つけて、装幀とタイトルに魅かれて買ってくれたそうだ。それまで私のことをまったく知らなかったが、いわゆる「ジャケ買い」だったのだという。ところが買って読んだらおもしろかったということで、新聞やテレビで紹介してくれた。それをきっかけに、彼との交友が始まった。
特に求めていない情報にも接することで、思いがけない機会が与えられることがある。こうした機会が、科学者の世界でも一般社会においても失われようとしている。
探したいと思う情報が
実は操作されている
物事をシステマティックにし、無駄を排して、効率化を極限まで進めているのが現代の社会だ。そんないまだからこそ改めて、目的に一直線に行かず、周囲を見まわしたり、寄り道をすることによる思いがけない出会いにも目を向けて欲しい。
特にAIが発達したからか、インターネットの検索サイトでは、こちらの興味のある情報やニュース、あるいは新刊本の紹介などを、過去の履歴から類推して、どんどん送りつけてくるようになった。こちらも興味のある情報が多いわけで、ついそれに引き込まれもするのだが、この頃は、私の過去に出版した著書の紹介まで送られてくるようになり、初めは苦笑いしていたのだが、これは実は怖いことではないかと少しずつ思うようになってきた。