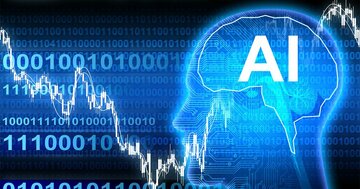この頃は特に、出たばかりの本に、発売たちまち何刷などといった景気のいい宣伝文句が使われるようになった。これは宣伝としては当然の戦略ではあろうが、それを受けとるほうのメンタルを危惧するのである。
何万部売れたという情報が最初に広告に出ることで、「流行に乗り遅れないように」という恐怖から「すぐ読まなくては」という方向へ意識が短絡するのである。
読むのをやめることにした
樹木希林の『一切なりゆき』
本そのもの、著者その人への興味から買うというより、「売れているらしい」という情報を鵜呑みにし、自分だけ取り残されたくない、という気持ちから、話題の本に集中する。まさに宣伝、広告がその本来の役割を果たしていると言えばその通りだが、怖いのは、買って読む、読んで満足を得ることよりも、「乗り遅れては大変だ」という意識そのものであるように私には思われる。取り敢えず読んだということが、充足感のすべてになってしまっているようなことはないか。
「これはおもしろい」とほんとうに自分が思っているのか、といつも自問自答することはとても大切だ。自分では「興味がある」「おもしろい」と思っていても、実はおもしろいと思わされていることがあるのだ。自分の考え方や行動は無意識のうちに、否応なく社会からの影響を受けるものである。
いまの学生たちを見ていると、「みんなが話題にするからこれを知らなければならない。知らないと話題から取り残される」と、取り残されることをとても恐れているように見える。一種の同調圧力であろう。圧力を感じる前に、先取りをして話題に飛びついていくというところが実態だろうか。
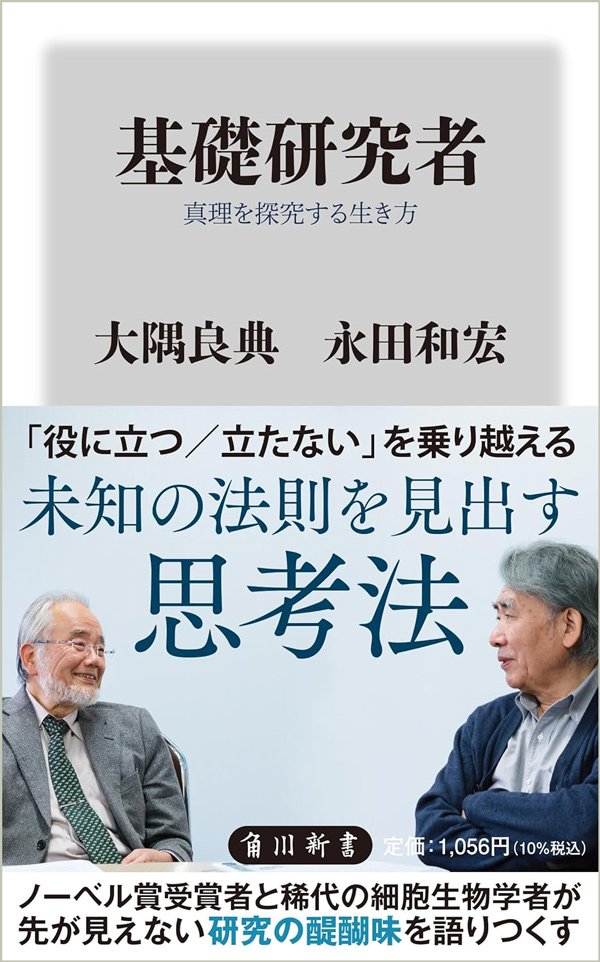 『基礎研究者 真理を探究する生き方』(大隅良典、永田和宏、角川新書)
『基礎研究者 真理を探究する生き方』(大隅良典、永田和宏、角川新書)
私は樹木希林という俳優が好きだった。特に是枝裕和さんの「歩いても 歩いても」をはじめとする一連の家族をテーマにした映画における、樹木さんの存在感は抜群であり、亡くなってすぐに出版された『一切なりゆき』(文春新書)はすぐに読んでみたいと思ったものだ。
ところが、発売されて3ヵ月で100万部を突破などという広告が各紙に載るようになり、私にはちょっと意固地なところがあって、それじゃあいまは読むのをやめておこう、となってしまった。どうも流行に乗るというのが嫌いなのである。いつかは読もうと思っているが、たぶんみんなが忘れた頃になるのだろう。