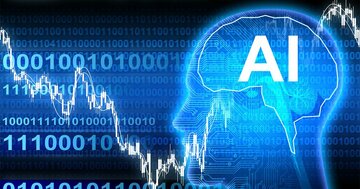私たちが、自ら探したいと思っている情報が、実は操作されている可能性があるのかもしれないということが1つ。
いまはもちろん過去の履歴などからの情報の提供ではあろうが、そんな形での情報だろうと思って、それらを重宝していたら、いつの間にか、情報提供者の操作する情報にどっぷりはまってしまっていて、こちらの興味そのものが操作されていたなんて、SFまがいのことも決してあり得ないことではないだろう。自分でそれに気づいていないというところがいちばん怖い。いわゆる「言論統制」といったかつての恐怖とある意味では隣り合わせの世界でもあろう。
それほど悪質でなくとも、もう1つ注意すべきは、自分の興味を忖度して、優先的に送られてくる情報にばかり接することによって、自分の世界がどんどん閉じていく危険性である。1つの世界にとことん詳しくなることも大切ではあるが、1つの世界だけに閉じこもってしまう危険性に注意深くあることもまた大切である。
皆が読んでいるからという
「乗り遅れ症候群」
情報の提供側のシステムがどんどん進化し、テクノロジーが発達して、必要な情報がすぐ手に入る。情報が向こうからやってきてくれる。これはありがたいことである。何より必要な情報にたどり着くまでの時間が飛躍的に短くなり、研究においても日常生活においても、すべてが効率化されているのを実感する。
そんな現在の情報社会に生きている私たちが、どこかで「乗り遅れる」ことに対する恐怖を醸成しているということはないだろうか。私は勝手に「乗り遅れ症候群」と呼んでいるが、誰もがすばやく情報を得ることができるようになったがために、それに1人アクセスしていないという乗り遅れ感というものが表面化しているようにも思うのだ。
たとえば本の売れ方を考えてみると、このところのベストセラーの出方はちょっと異常ではないかと思うことが多い。
私が最初にそれを思ったのは、永六輔による岩波新書『大往生』が、200万部を超えるベストセラーになったときだった。あるいはその少し前の、俵万智の歌集『サラダ記念日』(河出書房新社)のときだったかもしれない。何万部売れるなどということは、別に珍しいことではないが、200万という数字は、いかにも人工的な数字でしかない。200万人が自発的に読みたいと思って買ったというより、多分に、何万部売れている、何十刷を重ねているといった宣伝を見ての、集中的な買い方だろう。