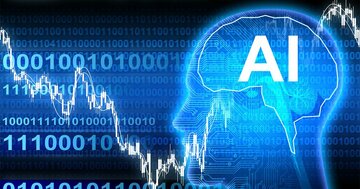Photo:Anadolu/gettyimages
Photo:Anadolu/gettyimages
現在、ネットで検索すればすぐに情報が手に入る。しかし、京都大学の永田和宏名誉教授は、それで「知る」ことはできても「分かる」ことにはならないと言う。現代のネット情報社会との向き合い方とは。※本稿は、大隅良典・永田和宏『基礎研究者 真理を探究する生き方』(角川新書)のうち、永田和宏による執筆パートの一部を抜粋・編集したものです。
ウィキペディアを見たら
「わかった」ことになるか?
知識を得るのは、学校だけでなく、いまやインターネットからという場合も多いだろう。言葉の意味だけではなく、複雑な疑問であっても、キーワードをいくつか入れることで瞬時に答えを出してくれる。検索の精度は加速度的に上がっている。
いまの学生たちはインターネットにアクセスすることで、知りたいことの多くを、即座に得ているように見える。会話をしながらでも、平気でウィキペディアで検索をしているような学生も多い。一義的にはそれで「知る」ことはできるだろう。しかしそれは果たして「わかった」ことになるのだろうか。
私は、なにかを知るため、理解するために費やす時間が、その長さが大切だと思っている。知りたいことがあって、すぐにわからなければ、その疑問はずっと頭の片隅に残っている。こびりついている。わからない間、もしかしたらこうではないか、ああではないか、と想像力が働く。これが答えだと思って確かめるとまた違う。そうすると再び、こうではないか、ああではないか、と想像する……この飽くなきプロセスによってこそ、想像力が養われていく。
インターネットはすぐに答えを得られるので便利な反面、「なんでかな」「こうではないかな」と思って疑問を抱え込み、自らそれなりに考えてみるという時間を少なくしている。これでは想像力が働く場面がない。
この、すぐに答えが返ってくるという時間感覚は、人々にどんな影響を及ぼすだろうか。
興味というのは、わからないことから湧いてくるものだ。最初からすべてわかっていたら、それは知識の対象にはなるだろうが、興味を持つ対象にはならないだろう。「わからない」部分があるからこそ、「知りたい」という欲求が湧くのである。「わからない」という時間にどれだけ耐えられるか、その耐えている時間こそが、〈知へのリスペクト(尊敬)〉を醸成する時間なのである。
どれくらい自分の中で問いや疑問を維持し続けられるか。この「わからない時間」に耐え、しかもそれを楽しむという習慣を、私たちはもっと大切にすべきだし、若い読者はぜひいまから心しておいて欲しいと思う。