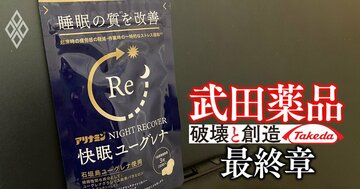Photo:医薬経済社
Photo:医薬経済社
光陰矢の如しと言うか、国内製薬業界再編の口火を切ったアステラス製薬の発足から、この4月で丸20年を迎えた。大卒で入社した青雲の志溢れる新入社員が、リストラの波を無事に乗り越えていれば、いささかくたびれ始める中堅クラスになっているくらいの歳月である。会社自体も、合併を主導した山之内製薬出身の竹中登一初代社長と藤沢薬品出身の故青木初夫初代会長が折に触れて見せたフロンティアを切り拓くのだという「情熱」は消えてしまったようで、小手先の弥縫策だけは得意な会社へと変貌してしまった。
当時、市場における存在感を一気に増しつつあった欧米のメガファーマに対抗しようと、併せて研究開発費は売上高の2割は最低でも必要だと喧伝されたことを受け、まず動いたのが両社だった。だが、その結果は周知の通り。第一に目指したR&Dの活性化はさして果たせず、青写真に描いた「グローバル・カテゴリー・リーダー」なるポジションも必然的に掴めなかった。逆に、図体が中途半端に大きくなった分、定期的に訪れるパテントクリフ対策に追われるのが経営の風物詩となった。
これをメガ外資の視座から眺めれば、我われに立ち向かおうとするのかと、しばしの間は注目したものの、結局は「蟷螂之斧」。近年は、クスリの種を求めて参勤交代してくれる極東の忠実なディストリビューターとしてカテゴライズされているものと想像する。
もちろんあの時、山之内と藤沢薬品が経営統合を選ばなかったら、恐らく両社とも、どこかに併呑されていただろう。占領されるぐらいならば、と意を決した点は今でも高く評価できよう。だが、合併の成就をフェーズ1とするならば、残念ながらその後の経営陣は、会社のあり方をフェーズ2へと進められなかった。漠としたビジョンやプランは示していたように記憶しているが、次なる目標像を明確に結べなかったためアクションが伴わず、文字通りの夢で終わった。
しかも組織として悪手となったのは、会社の「前進」がフェーズ1止まりとなった責任を誰も取らず、核心的問題の所在を美辞麗句で濁し続けたことだ。ほどなく、経営陣の発するメッセージに実態が伴わなくなり、上滑りが増していった。この行き着いた先が昨今、SNSでも話題となった岡村直樹社長CEOら同社経営陣に対する「信頼低下」である。
ちなみに「信」とは、「人の言葉」という意味を持つそうだ。言葉が疑わしいトップの元で働くのは、どんなに苦しいことであろうか。同社にはよく訓練された慎ましい社員が多いことを考慮すると、既に事実上の不信任を突き付けられている惨状に等しいと思われる。
アステラスの喫緊の経営課題が、27年に迫る前立腺がん治療薬「イクスタンジ」のパテントクリフであることは言を俟たない。約8000億円を投じて手に入れた加齢黄斑変性治療剤「アイザーヴェイ」の戦力化を急いでいるものの、欧州での承認プロセスが行き詰まるなど、雲行きが怪しくなっている。筋強直性ジストロフィー対象に開発中の遺伝子治療「AT466(開発コード)」も資産価値の見直しに伴う減損措置を強いられた。やることなすことが、至る所で裏目に出ているようである。