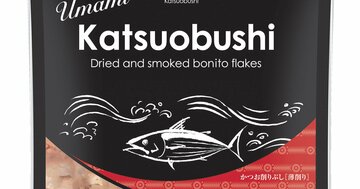日本の実情とともに、欧米、アジア、豪州、南米、中近東など19の国・地域の規制を調べた、A4版で92ページもある膨大な報告書だ。検査結果を待つだけになったので、年末の休日に読んでみた。
欧州では、EUの前身である欧州経済共同体(EC)が1990年に最初のプラスチック指令を定め、EUに組織替えしてからも2、3年おきに改訂を重ねてきた。
2002年には食品のリスクを調べる独立組織として「欧州食品安全機関」を設立し、加盟する28ヵ国の専門家が集まって検査方法や対象物質の研究を続けた。2011年には規制する金属や化学物質を定めた総合的な施行規則をまとめ、2020年には改訂版を発表して、検査する金属の範囲を広げ、検査方法も厳格化した。
技術の進歩に合わせた法改正が
日本はなかなか進まない
欧州の規制では、プラスチック容器に実際に食べ物を入れ、有害物質がどのくらい食品に移行するかを重視している。その検査では酸やアルコールに触れた場合や、さまざまな温度での移行量を調べるが、新しい規制では脂肪分が多い食品を電子レンジで調理した場合を想定し、最高175℃で検査する項目もつくった。
JETROの報告書は、欧州の規則は体系的・論理的につくられているために中国や豪州、湾岸諸国が採用し、いまや世界標準的な存在になったと言えると評価している。
では、日本の規制はどうなっているか。報告書は、昭和34(1959)年の「厚生省告示第370号」に基づいて説明しているが、「技術の進歩に合わせた法改正を永年しないために、使用実態との乖離があるのが現状である」と解説している。60年前の規制が現実とかけ離れたものであることは、だれでもわかる。
この課題について、国と産業界が約10年間、検討を進め、2020年6月、ようやく改正食品衛生法が施行された。しかし、検査する物質、検査方法などの具体的な事項は向こう数年かけて完成させることになりそうだという。
日本は欧米に比べて大きく出遅れたうえ、追いつこうとする作業さえものろのろと遅い歩みで、このままではさらに引き離されてしまう。そんな危機感が行間ににじむ。