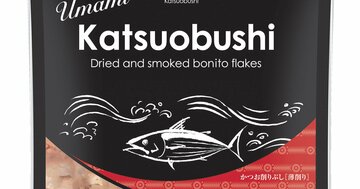聞いたことのない名前がいくつもあった。プラスチックの原材料となるテレフタル酸とエチレングリコールが、いくつかの条件のもとでどのくらい溶出するかについても検査結果を求めていた。さらにプロピレンなど5種類の添加剤、原材料などについても記入する欄があった。
60年以上前に定めた基準を
日本は使い続けていた
豆腐パックのメーカーに検査結果を送ってくれるよう、代理店である泰喜物産の落合利治さんを通して頼んだ。落合さんは開業時に駆け付けてくれた豆腐づくりの先生である。
落合さんから届いた「分析試験成績書」は日本食品分析センターという財団法人が作成したもので、カドミウムと鉛の2種類しか検査しておらず、結果欄には「適」とだけ記載されていた。
溶出試験は(1)ヘプタン、(2)エタノール、(3)水、(4)酢酸の4種類について数値が書かれていたが、欧州連合が求めている樹脂の原材料や添加剤など7種類の化学物質はどれも検査対象になっていなかった。
成績書の欄外に小さな文字で記された「注」を見て、びっくりした。「規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の合成樹脂製の器具または容器包装」と書かれている。昭和34年は1959年だ。なんと61年も前に定められた基準がそのまま使われているのだ。最初の東京オリンピックより、さらに5年前である。「厚生省」も昔の名前であり、労働省と統合して「厚生労働省」となってから、もう20年も経っている。
EUの規制内容は
2、3年おきに改訂されている
食品用プラスチック容器に対する日本の規制は、欧州とはあまりにも違いすぎる。60年前の規制は、のちに化学物質がいくつか加えられたが、基本は同じままで、まだ日本で通用している。
ほかの国ではどのように規制しているのだろう。その疑問に答える資料が、全豆連(編集部注:「一般社団法人 全国豆腐連合会」の略)の相原事務局長のメールに添付されていた。日本貿易振興機構(JETRO)がこの年、2020年3月に発表した「海外向け食品の包装制度調査」だ。