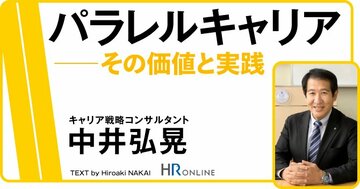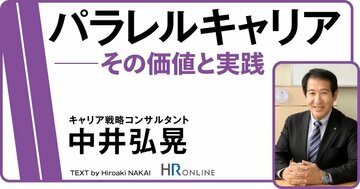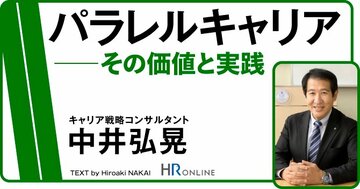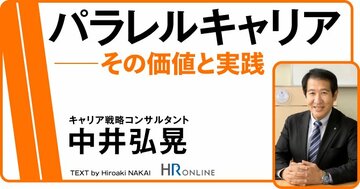「滅私奉公」が通用しなくなった3つの理由は…
「活私奉公」に直接触れる前に、この造語のベースの言葉であり、ミドル・シニア世代であれば誰もが知っている「滅私奉公」について考えてみます。
「滅私奉公」は「滅私」と「奉公」が組み合わさった言葉で、私利私欲(個人の利益や願望)の追求を捨て(「滅私」)、公(国や社会)、所属組織や上の立場の人のために尽くす(「奉公」)ことです。字面をそのまま読むと、日本人の美徳ともいえる考え方であり、模範的な姿勢のようにも感じますが、自己犠牲の行き過ぎによる過労死問題や戦時下での全体主義などの弊害を生みました。一方で、この「滅私奉公」という自己犠牲的で献身的な姿勢が日本の高度経済成長を下支えした考え方であったことも事実です。
しかし、現在は、「滅私奉公」の時代ではありません。
その理由を3つあげます。
1つ目は、時代が変わり、最低限の生活が保障されるようになった点です。人権に対する考え方も大きく変わりました。
日本のドラマ史上最高視聴率(62.9%)を達成した『おしん』というテレビ番組がありました。1983年から1984年にかけてNHKで放映された戦中・戦後の混乱期をたくましく生きた女性の一代記です。なかでも特徴的なシーンは、困窮した家族を助けるために(口減らしのために)、7歳のおしんが自分を犠牲にして年季奉公(主人と従属する奉公人の間で時限的に労働等を提供する身分形態)に出た場面です。日本が貧しかった時代、家族を養うため、自分を犠牲にしても働く必要がありました。しかし、多くの国で合法とされていた年季奉公は「人権侵害」が理由で禁止されており、現在、合法には存在していません。
2つ目は「滅私奉公」して所属組織のために働いても、それが必ずしも報われることがない時代を私たちは生きている点です。1970年代の高度経済成長期においては、自身を犠牲にして働いたら、組織が処遇面で応えてくれました。収入も働けば働くだけ増え、企業にいったん入社したら、企業が個人を丸抱えして定年まで面倒を見てくれました。社員もそれを良しとしました。入社後には、企業がOJT、Off-JTを準備し、組織が敷くレールに乗っかっていれば、ある程度の地位や収入が定年まで保障されていました。社内での仕事だけに目を向けていれば十分で、自分自身が将来のキャリアを考え、計画し、行動する、いわゆる自律的なキャリア形成に取り組む必要もありませんでした。脇目をふらずに社内業務に専心し、社内政治に精通することが出世のいちばんの近道でもあった時代です。
いまはどうでしょう? 年功序列制度の廃止、終身雇用制度の崩壊、役職定年制度・定年再雇用制度の導入、早期退職制度などが展開され、エスカレーター的にゴールまで無事に運んでくれると信じていたミドル・シニア世代には、厳しい現実が突きつけられています。梯子を外されたと感じ、モチベーションを低下させてしまったミドル・シニアも多くいます。そんなミドル・シニアを目にする若手世代は、自分を犠牲にして組織に尽くしても、見返りが期待できない時代となっていることを実感しています。
3つ目は、「滅私」を強いることが若手社員の早期離職につながる点です。
最近の大学生のなかには、「会社は自身の能力を発揮するプラットフォーム」という捉え方をし、「自身のスキルを高められ、自らを成長させる場で仕事をしたい」と考える人が増えています。私はそれでいいと思います。簡単に即戦力となることは難しいにしても、貢献したいという思いやプロ意識は個人にとっても組織にとっても重要です。そうしたなか、会社はうかうかできません。学生時代からキャリア教育を受け、意識の高まった新入社員は企業の姿勢を敏感に察知します。「(会社が)個人のスキルの展開に無関心」「この会社にいても自身が成長する見込みがなさそう」と判断した若手社員は、さっさと見切りをつけて転職へと向かいます。「生涯1社勤務」が常識で、「転職」という選択肢が発想としてなかった現在のミドル・シニア世代とは全く異なります。
最近、物価の上昇に対応して、賃上げや新卒の初任給アップの話がニュースで頻繁に取り上げられています。賃上げや初任給のアップは、優秀な学生を採用するためにも、若手社員の早期離職を防ぐためにも必要な措置であることは確かです。しかし、処遇面の改善以上に、個人が能力を発揮できる環境を整え、モチベーションを高めることが、より大切だと私は思います。所属組織が自身(個人)の力を活かす絶好のプラットフォームであり、自己実現につながる場だと感じられる場合、社員はそう簡単に辞めません。社員にとって働き甲斐のある会社にすることが、より抜本的な離職抑制策です。個人の意識の変化のスピードに負けないスピードで、組織も意識改革、組織変革をしていく必要があります。