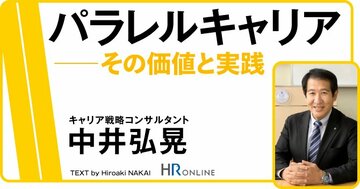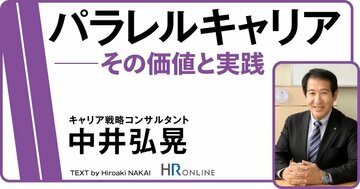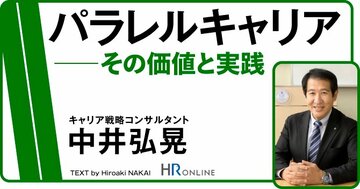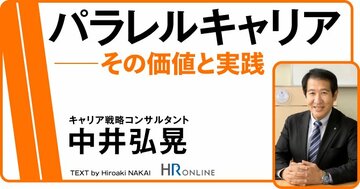「奉公」的な愛社精神がWIN-WINの関係をつくる
私は、「滅私」ではなく「活私」の時代だからといって、「私利私欲」に走ることや、「自分さえ活かすことができればいい」といった利己主義的な考え方を勧めているわけではありません。そうした誤解を防ぐためにも「活私」の後に続く「奉公」という言葉が大切になってきます。時代遅れとも思える「奉公」という表現を、あえてそのまま使う理由を2つあげます。
1つ目は、時代が変わり、個人と組織の間の関係が希薄になってきているからです。昔ながらの「奉公」という言葉を残すことには、社員として給料をもらっている以上、しっかりと、組織に奉仕し、貢献する必要がある点を意識してもらいたい意図があります。「誰かの力になりたい」という思いが、自身を成長させるきっかけとなることもあります。
時代の経過とともに、変えていくべきことと変えずに維持していくべきことがあるはずです。変えるべきことは、コンプライアンス、人権、多様性を従来よりも尊重して行動することであり、変えるべきでない点は、感謝する気持ち、貢献、奉仕の心だと私は思います。
2つ目は、「奉公」という言葉は組織心理学の世界で重要視されている「組織コミットメント」や「従業員エンゲージメント」に通じるところがある点です。企業力を高めるために組織が注目している「組織コミットメント」や「従業員エンゲージメント」は、個人が自身の能力を活かしながら、組織に奉仕し、貢献できていると感じるときに高まります。私自身の経験則ですが、仕事量が少ないときや給料がアップしたときよりも、たとえ忙しくても、自分が納得のいく仕事ができ、上司や組織から正当に評価されたときに、仕事に向かう活力やモチベーションがより高まりました。こうしたサイクルが適切に回ることによって、個人の「組織コミットメント」(愛社精神)は強まります。
私は、「愛社精神」は、時代に関係なく重要だと考えています。「愛社精神」を社員が抱ける会社というのは、組織が個人を大切にし、活かしていることの裏返しともいえるからです。会社の売上・利益至上主義で、社員に自己犠牲を強いる企業、倫理的に問題のある企業、多様性を尊重しない企業などに対して、社員は決して「愛社精神」を持つことはできません。
戦中・戦後まもなくの時代から、価値観や生活様式、個人にとっての仕事に対する位置づけも大きく変わり、組織と個人は従属する関係でも、対立する関係でもなく、両立する関係が望まれる時代となっています。