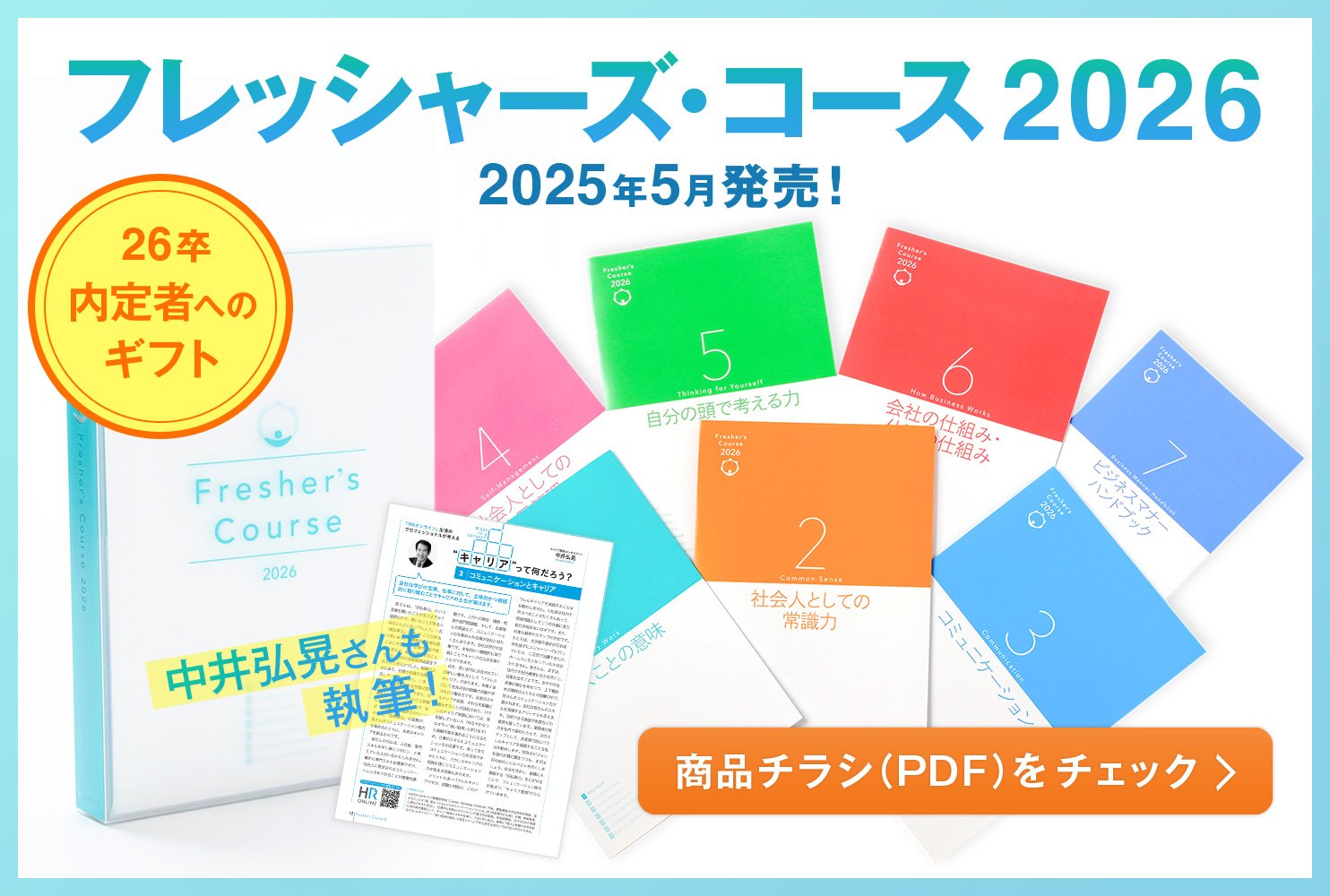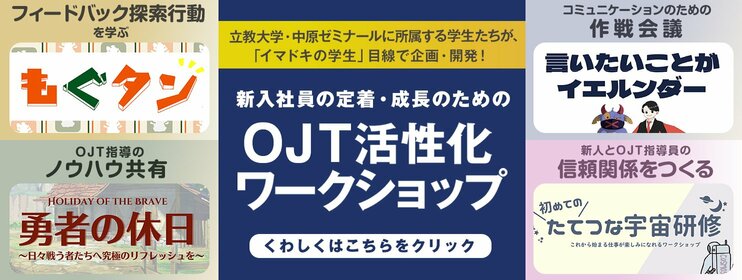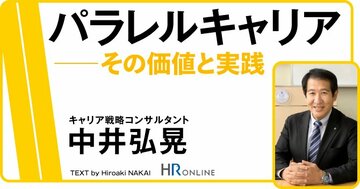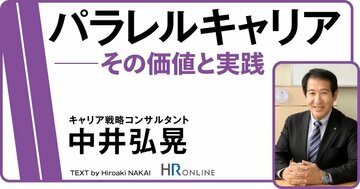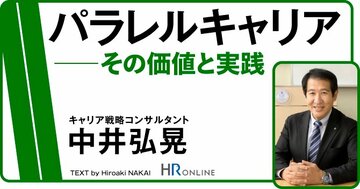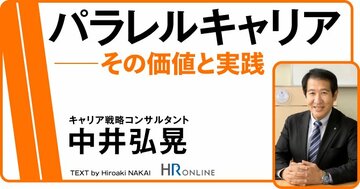学び続け、所属組織に貢献するのが「活私奉公」
現在、日本では「ワークライフバランス」の考え方が浸透し、随分と働きやすい環境になりました。「働き方改革」においても長時間労働の解消が一つのテーマとなり、残業や休日出勤も減少しました。「ワークライフバランス」は、ある意味、「滅私奉公」の負の側面への対応策の一つであり、一定の効果が出ているとも思います。残業の減少により、プライベートの時間が増え、子育て、家事、趣味、介護などさまざまなことに時間を費やしやすくなりました。ただ、これからは、ワークとライフを切り離す(分離する)考え方からさらに一歩進んで、ワークとライフのシナジー(相乗効果)を目指すべき段階ではないかと、私は考えます。
ワークはライフの一部であり、生きていくうえで仕事の比重は極めて大きく、ワークの充実なくしてライフの充実は極めて難しいからです。
私たちは、決して自らを犠牲にすることなく、しっかりと所属組織に貢献しながら、自身のキャリアを成長させることができる「活私奉公」の時代に生きています。従来とは異なり、キャリアのハンドルを自分自身で握れる時代です。ただし、ハンドルを握るためには必要条件があります。それは、自らが「専門スキル」を身に付けていることです。「専門スキル」もないまま、自身の「希望職種」や「希望部門」で仕事ができるほど会社は甘くはありません。
では、どのようにして「専門スキル」を身に付ければいいでしょうか? まず、担当業務について、社内での第一人者を目指して、全力を尽くすことです。「専門スキル」は、一定期間、「必死」の努力を継続して初めて身につくものです。あわせて、業務と関連する公的資格を計画的に取得することをお勧めします。そして、次のステップとして、社外での武者修行ともいえる“パラレルキャリア”に取り組み、実戦力に磨きをかけましょう。ここまでできれば、「活私奉公」の姿勢を持ちながら、キャリアのハンドルを自身で握れる可能性はぐっと高まります。
それでも、組織に属している以上、出向や転籍など予想外の人事異動辞令が出ることもあります。どうしても納得がいかない異動辞令に対しては、スキルを活かしての転職や独立という選択肢もあるかもしれません。しかし、転職や独立はあくまでも最後の手段であって、まずは所属組織内でいかに貢献できるかの道を探ることが先決です。前々回(連載第5回)でも触れましたが、異動は、新たな「専門スキル」を身に付ける機会にもなり得るからです。焦らずに、「損して得取れ」の意識でいいと思います。
“活私奉公”の時代に、ビジネスパーソンは仕事にどう向き合えばよいか?――周囲への感謝の気持ちを忘れず、自分を大切にしながら、社内外のさまざまな機会を活用して学び続け、所属組織に貢献することです。「活私奉公」を意識した働き方は、組織への貢献度と個人のエンプロイアビリティ双方の向上につながる点で、まさに、いま求められるものだと私は思います。