遺伝子についてはある程度学校でも教わったはずですが、突然「遺伝子って何ですか」「DNAって何ですか」と聞かれても、大半の人はあまり説明できません。ふわっとした理解にとどまっているんです。
それが悪いわけではないのですが、遺伝子とDNAの違いは何か、DNAとRNAの違いは何かなど基本的なことを知らないと、人間はどう行動するでしょうか。
結局は自分が知らない、よくわからないものよりも、自分の理解がおよぶ範囲で安全とわかるもの、昔から食べられている自然のもののほうを選びます。それは当然のことですよね。
それが大きなうねりになって、世論として「遺伝子組換え」は不安という議論になるんじゃないでしょうか。
昔ながらの、自然な製法で育てられた食材のほうがいいと判断するのは、自分を守るための考え方として、決して不合理なことではないと思います。ただ、自然のものが全部安全で、人工のものが安全でないのかというと、必ずしもそうではないはずです。
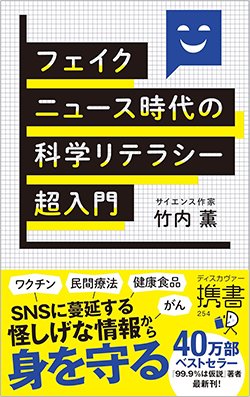 『フェイクニュース時代の科学リテラシー超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、ディスカヴァー携書)
『フェイクニュース時代の科学リテラシー超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、ディスカヴァー携書)竹内 薫 著
農作物だって、科学的な工夫をすることで安定した生産を実現してきました。農薬の開発や品種改良が進んできたおかげで、作物ができなくて飢饉になることも現在はありませんし、農家の人たちは安定して暮らすことができます。
自然農法によってつくられた作物を、一部の人が高い値段を出して買うのはまったく問題ありません。多様性があって、むしろいいと思います。
ただ、社会全体として自然なやり方を大事にしようといった方向性になると、最悪の場合、飢饉(ききん)が起きて食べるものがなくなったり、それによって大勢の人が飢えて死んでしまったりするわけです。そして、それも自然が持つ別の側面なのです。
自然派志向というのはある意味、科学が社会を発展させたうえで成り立つものです。
自然につくられた作物を買うと気分がいいという、個人レベルだからこそ可能な、一種の贅沢なんですね。







