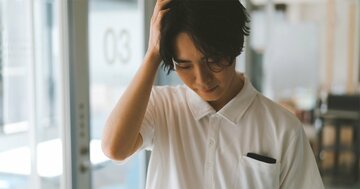写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
医療の進歩と高齢化の影響により、日本人の死生観は大きく変わった。生と死の選択肢として、延命治療や緩和ケアなどが入ってきたからだ。しかし、納得できる死を「創る」には、そうした医学的な対応だけでは不十分だと著者は言う。人生の最期をどう生き、死後に何を遺すのか。今一度考えてみたい。※本稿は、柳田邦男『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)の一部を抜粋・編集したものです。
納得できる死を「創る」には
医学的な対応だけでは不十分
ここ30年ほどで日本人の死生観は大きく変わりました。医学の進歩と高齢化が背景にあります。
死因の1位であるがんにしても、ただ延命治療するだけではなく、痛みや苦しみを取り除く緩和ケアが治療の選択肢に入るようになりました。生と死の選択について、個々人の意思が問われる時代になったのです。
「死生観」を考えるには、3つのフェーズに分けるのがよいでしょう。どのように死を迎えたいか、死を目前にしてどのように生きるか、そして死後に何を遺すのか。これらを3つに分けて考える必要があります。
終末期に納得できる医療を受けるには、日頃から地域の医療状況について把握しておく必要があります。自分のまちの病院やホスピスの事情、在宅で緩和ケアを施してくれる医師がいるのか。事前に準備をしておけば、病気が進行してきたときに、どういうかたちで最後の日々を過ごすかスムーズに選択できるわけです。
ただし納得できる死を「創る」には、痛みや苦しみを取り除くという医学的な対応だけでは不十分です。
最も重要なのは、死が避けられなくなったときにどう生きるか。心おきなく最期を迎えるために残された時間で何をしたいのか。これに関しては誰かが答えを出してくれるわけではない。自分で考えるしかありません。
医療者や家族のサポートで
患者の最期は大きく変わる
どんな人であれ、山あり谷ありの物語を生きている。振り返るといくつものエピソードがあって、それぞれが人生の1章1章を構成しています。死の直前というのはその最終章です。物語をどう完成させるか。未完で終わらせないで、その人らしくどう生きるか。自分の死は自分で創らなければならないのです。
医療者も、患者が本当に納得感のある死を迎えるにはどうすればいいか、という意識を持たなければなりません。患者の人生観や死生観や当面のニーズをくみ取り、どうサポートできるか考えることが真の役割なのです。家族も同じです。医療者や家族が伴走者となって心身両面のサポートをしてくれると、患者の最期は大きく変わります。
ある鉄工所の親父さんの話が象徴的です。大学病院で肺がんの治療をしていたのですが、がんが骨転移し苦しんでいた。緩和ケアが十分でなかったために、家族が見舞っても当たり散らすような状態でした。