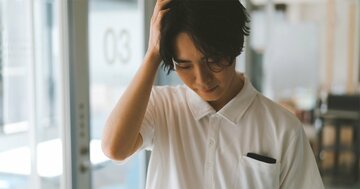本人の希望は「家族に囲まれて家で死にたい」というものでした。退院して、自宅で微量のモルヒネを服用すると、痛みがころっと取れた。家族が一体となり親父さんを支えました。お孫さんに「おじいちゃん頑張れ」と背中をさすってもらい、本人は「地獄から天国へ帰ってきた」と喜んだそうです。「俺は幸せだ、俺は幸せだ」と毎日言い続け、それが最期の言葉になりました。
私自身も“最終章”を考えています。残り少なくなったらなるべく家にいて、平凡な日常生活を送りたい。台所で朝食を用意したり、夕食に何か1品を作ったりというのが好きだから、そうしたことをマイペースにやっていきたいですね。
それから、趣味で撮ってきた雲の写真を整理して、写真集と絵本を作りたい。少年時代には気象台の測候技師になりたかったほど、人生を通じて雲に魅せられてきましたから。
父からもらった
“静かな死”という財産
現代は死をイメージしにくい時代です。戦争がないということが大きい。病気であっても、家での看取りが圧倒的に少ない。死は遠い存在になってしまいました。
私の場合は、少年時代に次兄や父が自宅で亡くなっているので、体に染み付いた死と看取りの経験というのがあるんですね。
終戦直後の昭和21年(1946年)のことです。僕は6人兄弟の末っ子で、小学3年生でした。2月の静かな朝、肺結核のため自宅で療養していた上から2番目の19歳の兄が旅立ちました。
同じ年の夏に、やはり結核で父が亡くなりました。父は意識が薄れる前に家族を呼んで、1人ひとりの手を握って言葉をかけてくれました。私には「健康第一だからな、体を大事にしろよ」といってくれました。家族を集めたのが朝の9時頃で、2時間余り経ってお昼前に眠るように逝きました。
私はその瞬間、離れた部屋で独り涙を流していましたが、母に呼ばれて父の枕許に行き、母に教えられたとおりに、死に水をとりました。
父からもらった最高の財産は“静かな死”だと思っています。父の死の場面は、いまだに忘れようもなく、私の記憶に染み付いています。1番人間らしい、自然な旅立ちだという気がするんですね。
私の死生観に関してはもう1つ、70年代の終わり頃から、ノンフィクション作家として、がん医学を中心とした生と死の問題を追いかけてきたことも大きいですね。これまで数百人くらいの闘病記を読んできました。闘病記を通じて知った数百人の死の積み上げで、死ぬ瞬間の多様なイメージができてきたのです。