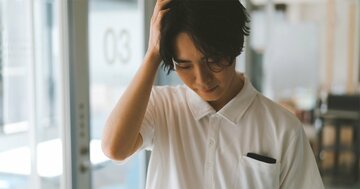だから、死がイメージできない人には、闘病記を読むことを勧めます。よい闘病記を読むことは、死を迎えるためのいわば問題集をこなすのと同じこと。自分の死というのは、人生における最後の入学試験だと思えばいい。少なくとも40歳を過ぎたら、人間の生き方と死に方について学んでおくべきでしょう。
死後も残る
“精神性のいのち”
死生観には方程式のようなものはありません。自分が体験したり本を読んで積み重ねたりした、ストーリー性のあるものでないと自分なりの“死の戦略”を立てられないのです。
死んだ後、いったい自分はどこへ行くのか。死への不安や恐怖の原因になるのがこの問題です。
私は死後の世界というのをはっきりと認識しています。あの世があるのかないのか、ということを問うても答えはない。しかし、人間の“精神性のいのち”という視点で考えれば、答えは意外と簡単に出てきます。
私のケースで考えてみると、父親は生きているわけですよ。父を看取った思い出がすべて、私の心の中で鮮やかな情景となって残っている。
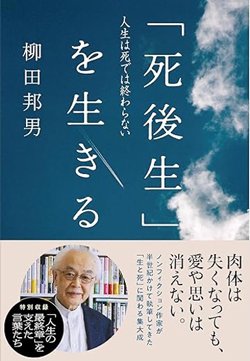 『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)
『「死後生」を生きる 人生は死では終わらない』(文藝春秋)柳田邦男 著
実家を離れ独立していれば、親が生きていても、年に数えるほどしか会う機会はありません。生きている親を敬って心の中で生かしているような人は、むしろ少ないでしょう。しかし不思議なことに、死ぬと“精神性のいのち”が残るのです。何かあれば、親の生き方や言葉が甦ってきて、人生の道しるべになってくれる。
つまり人間の“精神性のいのち”は死後も成長し続けるのです。そう考えると、本当に納得できる最後の日々を送らなければならないし、最後の日々をよりよく生きることが“死後の未来”つまり「死後生」につながるのだという希望さえ湧いてきます。
私は孤独な死を迎えることになっても、耐えられると思っています。自分が最後をどう生きるかということを考えたとき、愛する人がいることは最高ですが、仮に先立たれて独りになっても、忘れ難い日々や言葉を回想し噛みしめつつ、自分の内面と生き方を絶えず見つめていくなら、人生をきちんと全うできる。
私はそれくらい腹の据わった精神性を持ちながら、最期の日々を送りたいと思っています。