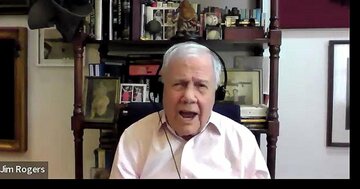ディスカッションが緊急開催されたのは、自民・公明・日本維新・国民民主4党らの議員連盟が「特定生殖補助医療法案」を参議院に提出したのを受けてのこと。この法案はもともと、AIDで生まれた子の〈出自を知る権利〉の保障が目的だった。
ところが、提出された現行案では肝心のその目的が全く達成されていない。問題点は大きく二つある。一つは、当事者の声を聞かずに拙速に議論を進め、真の意味での〈出自を知る権利〉が保障されていないこと。もう一つは、生殖補助医療の対象が「法律婚の夫婦」に限られることだ。
【2月5日提出「特定生殖補助医療法案」の要約】
特定生殖補助医療の適正な実施を確保するための制度、特定生殖補助医療により出生した子が自らの出自に関する情報を知ることに資する制度等について定める。
1. 医療を受けられるのは、法的夫婦のみ。
2. 精子・卵子の提供者の情報、その医療を受けた夫婦、出生した子の情報を国立成育医療センターにおいて100年保存。
3. 出生した子は、成人に達した後、以下のことをセンターに請求・要請できる。
(1) 自らの情報の保存の有無の確認
(2) 提供者の個人の特定しない情報の開示(身長、血液型、年齢等)
(3) 提供者を特定できる情報を、センターを通して本人に要請(提供者は拒否することができる。提供者に決定権がある)
(4) 提供者が死亡していた場合には、氏名の開示(提供当時の同意があるとき)をセンターに請求できる
日本におけるAIDは1948年から慶応義塾大学医学部で始まり、生まれた子は1万人以上いると言われる。しかし、長らく親が子にその事実を伝えないことが慣習だった。そのため、何らかの理由で出自を知った当事者(大人になってから知ることが多い)は、アイデンティティの喪失などに陥り、悩みや苦しみを抱える人も多い。
筆者は2010年頃からAIDで生まれた子や医療関係者などを世界中で取材し、『私の半分はどこから来たのか』(朝日新聞出版)を出版した。この本に登場するAIDで生まれたイギリス人男性は、「考えれば考えるほど、自分の生物学上の父親が誰か分からないことの重みに、打ちひしがれる思いでした」と打ち明ける。
「生物学上の父親を探し出すのは、自分のエネルギーを使い切り、精神的に消耗させられるものでした。ドナーかもしれないと思われる人や、提供情報記録を調べるのに費やした時間は計り知れません。その間、私は学生時代を楽しむどころか、余裕が全くなかった。そうならざるを得なかったことに強い怒りを覚えます」(同)
そして彼は、ついに父親に会うことができた後、「もう父親探しをする必要がなくなった。それが何よりもの安堵感だった」と語った。
繰り返しになるが、日本にはすでに、第三者から提供された精子や卵子で生まれた人が1万人以上いる。彼・彼女らは、〈出自を知る権利〉についてどのように思っているのか。『私のお父さんは誰?慶應大病院「精子提供」で生まれた人が訴える切実な理由』では、当事者の声を紹介し、今般提出された法案の問題点を詳しく解説する。
 オンライン・ディスカッションの様子
オンライン・ディスカッションの様子