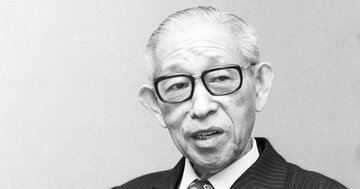筆者は、イスラエルがなぜ起業や経営になじみ深い社会的・文化的規範を持つのかについて調査したことがあります。
その結果として浮かび上がってきたのは、(1)ユダヤ教の『タルムード』という経典が実質的には人生経営学の教科書となっていること。(2)会社だけでなく人生も趣味も仕事も病院も学校も経営だという考えを親が子どもに教えていること。(3)イスラエル政府一丸となって問題解決教育を幼児期からおこなっていることなどが分かりました。
つまりイスラエルでは、教会、家庭、学校といったあらゆる場面で経営教育がおこなわれているのです。
戦後日本とユダヤ教徒に学ぶ
選民思想じゃない“和の経営教育”
イスラエルに住む人々に限らず世界各国に散らばっているユダヤ教徒は、幼少期から一種の価値創造の英才教育を受けているわけです。イスラエルには十分な土地もなく、中東とはいえ石油も豊富ではないという特徴があります。世界各国に散らばるユダヤ教徒(ユダヤ人)は、長らく国を持たない流浪の民でした。
だから、人間の脳みそと身体という資源に頼るしかないために、宗教的・文化的にこうした教育をおこなってきたのではないでしょうか。
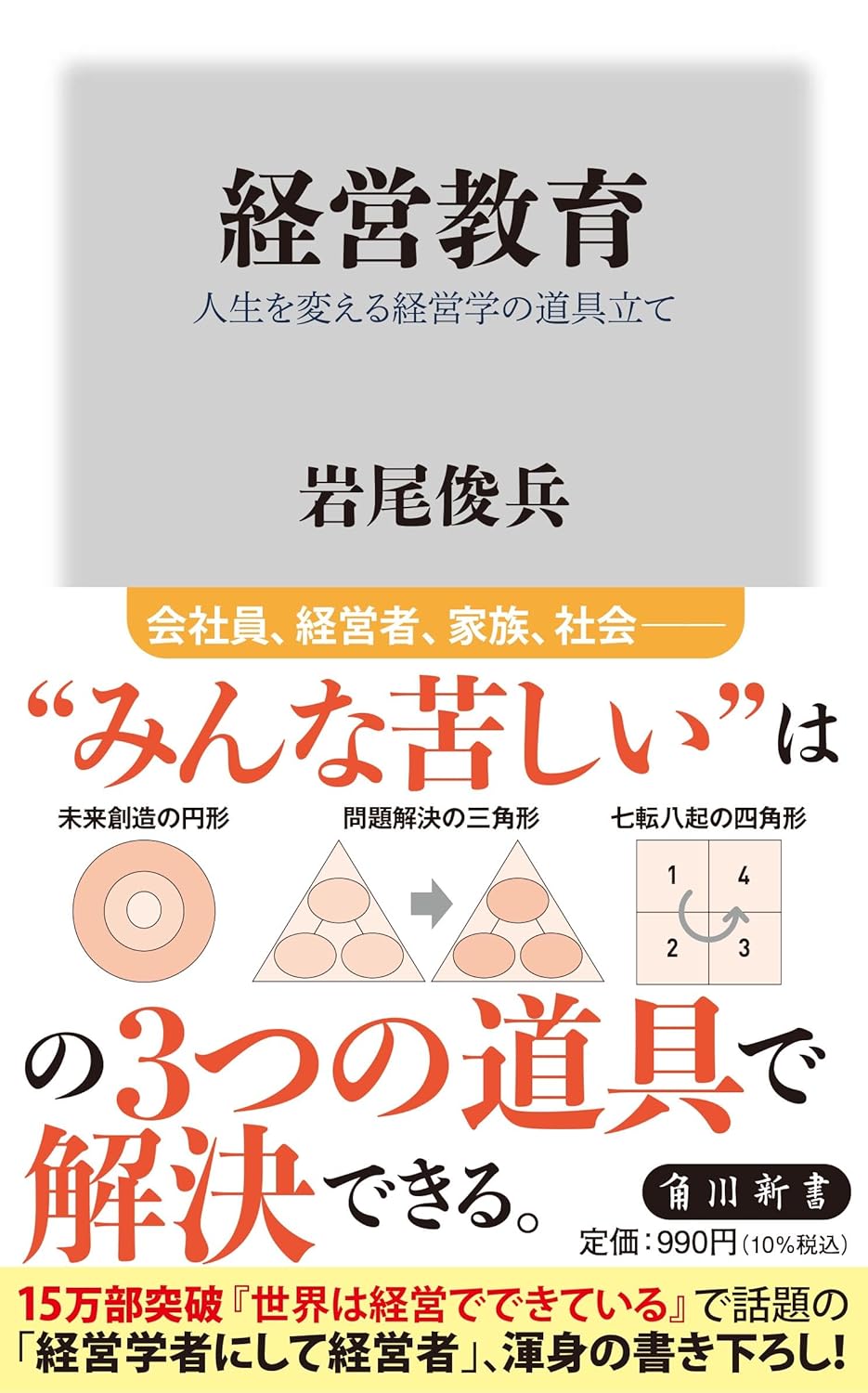 『経営教育 人生を変える経営学の道具立て』(岩尾俊兵、角川新書)
『経営教育 人生を変える経営学の道具立て』(岩尾俊兵、角川新書)
この状況は何かに似ています。そう、戦後日本です。
戦後日本はすべてを失いました。土地も在外資産も機械も建物もです。そこで頼れるのは人間の脳みそと身体だけ。ですから価値創造の民主化を目指し、経営教育を薄く広く国民に広めていきました。その結果として世界第2位の経済大国に短期間でのし上がったのです。
やはり経営意識と経営知識を社会で薄く広く普及させることのメリットは大きいということが傍証されると思います。
一方で、日本にはユダヤ教的な選民思想はなじみません。日本には集団を大切にする和の心があります。だとすれば、日本では「自分だけが儲もうければいい」という思想ではない形の経営教育が可能だといえないでしょうか。
すなわち、日本は東洋的な和の心を持った価値創造の民主化によって、「みんなで豊かになる」という理想を実現できる国になれると思うのです。