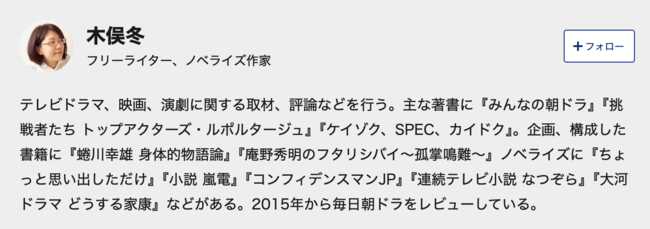アンパンマン誕生までの伏線だけでなく
やなせたかし論も盛り込む“巧妙さ”
『アンパンマンの遺書』(岩波現代文庫)の「銀座学校」の章で、当時、やなせが心惹かれた様々なカルチャーについて書き、そのなかに「このフランケンシュタインと井伏鱒二と太宰治と、その他いろいろがごっちゃになって、後世アンパンマンをかく伏線となる」という一節がある。
井伏鱒二も「さよならだけが人生だ」はすでに『あんぱん』第21回で出てきている。太宰治は井伏鱒二の弟子ということで読んだそうだ。
フランケンシュタインはともかくとして、井伏鱒二、太宰治と聞くとやなせは教養人だと現代人の我々は思ってしまうが、やなせは「怪しげな教養」と書く。「ハイレベルのインテリゲンチアには生涯なれなかったし、なる気もない。通俗が性にあっている」というやなせの述懐を読み、なるほどと合点がいく。
「何のために生きるか」や「逆転しない正義」など、やなせが掲げるテーマは哲学的でやや説教くさい感もある。それをたっぷり内包する『アンパンマン』が子どもを中心に大衆にヒットした理由は、やなせの土台が先鋭的過ぎず、通俗的だからなのだろう。人生論を理屈っぽくこねくりまわさず、あくまでも素朴な発想なので親しみやすいのだと思う。
「アンパンマンを描く伏線」というものをドラマに落とし込み、さらには、やなせたかしとはなんだったのか論もさりげなくドラマに仕込んでいるところが、『あんぱん』の巧妙なところだ。
銀座ですっかり開放的になった嵩は、のぶに手紙を書く。自由で楽しそうで、銀座には美人がたくさんいると書く様子に、自由を奪われたのぶは、憤慨する。
嵩がこの手紙で一番言いたいことは、のぶと一緒に銀座の景色を見たい、ということなのだけれど、残念ながらものごとはなかなか正しく伝わらないものなのである。
この手紙の差出人は「嵩子」と女性の名前になっている。やっぱり女子寮に男性から手紙がくるのは咎められるのだろう。嵩もそこはちゃんと気遣える人のようだ。