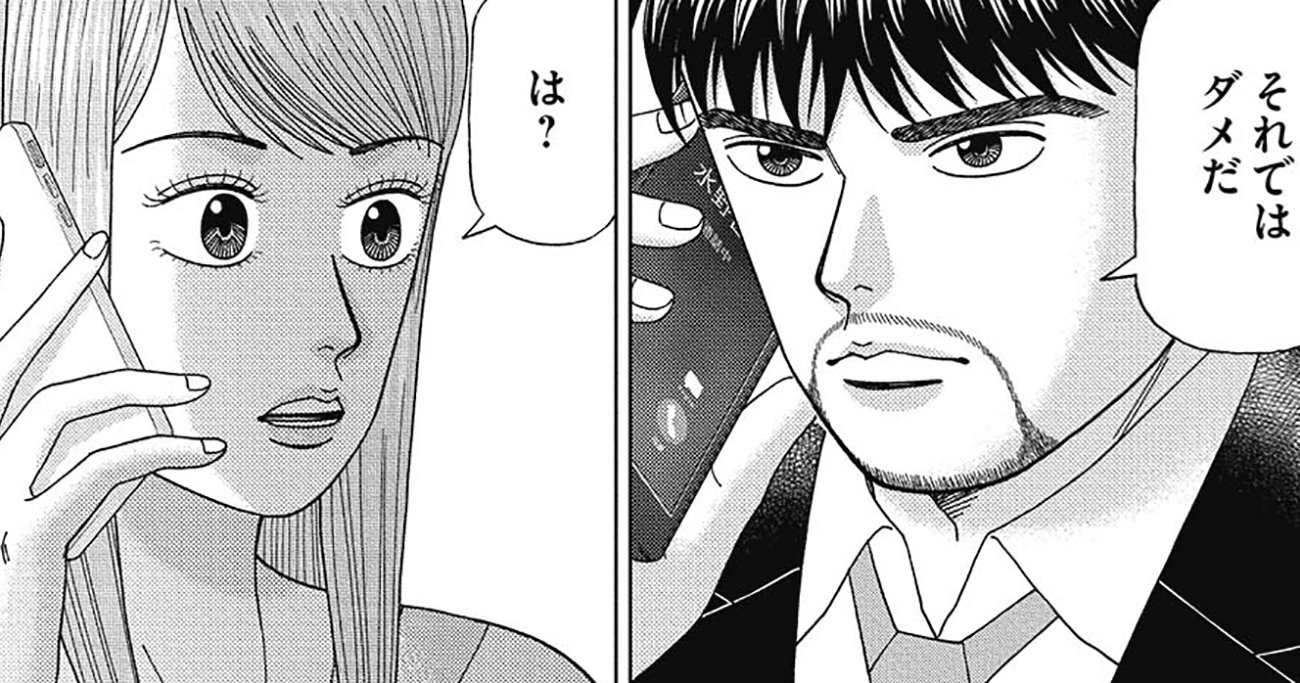 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第54回は、「大学受験は個人戦か団体戦か」について考える。
不合格続出の原因は…
勉強合宿から抜け出して帰宅しようとした天野晃一郎と早瀬菜緒だったが、電車内で単語帳を開く同年代の生徒を見つける。「東大を目指す人はみんな今勉強してる。自分も早く戻ってやらなきゃ」「あの人たちに負けられない!」と思い直した2人は、勉強合宿に引き返すのだった。
「受験は団体戦」と言われる。そしてまた同じくらい、「受験は個人戦」とも言われる。確かに、塾や学校・友人関係などの雰囲気が受験に大きな影響を与えることは間違いない。
中学受験の例ではあるが、僕が通っていた塾で過去にこんなことがあった。最上位クラスの生徒が軒並み、志望校に不合格になってしまったのだ。中には開成中学志望で全国上位の超好成績をおさめた生徒もいた。その原因の1つは間違いなく、クラス内の男女が対立してしまい、雰囲気が険悪になってしまったことにあった。
東大で出会った私の友人は、同じ科類を志望する高校の同級生に配慮して、志望科類を変更したという。少しでもその人のための枠を確保しよう、という思いからだ。友人の成績はいい方だったとはいえ、個人戦として考えると賢い選択とは言い難い。
もちろん、互いに励ましあったり情報を集めやすかったりと、集団で受験に挑むことはメリットもある。だが、この諸刃(もろは)の剣の裏にはもっと根深い問題があると思う。団体戦にしろ個人戦にしろ、他者との競争意識が無意識にあおられている、ということだ。
テストの点数から100m走に至るまで、競争は、常に数値が結果として出ることを前提とする。数値の存在は魅力的だ。互いに比較してその優劣を客観的に示すことができる。だが、それは「競争自体を目的としている場合」のみの話だ。
学びを“数値化”することの弊害
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
そもそも、勉強は競争を目的としていない。ただ純粋に、わからないことを解き明かしていく営みにすぎない。その環境を獲得するためのステップの一つとして、それまで勉強してきたことを確かめる受験があるのだ。勉強において「競争」とはあくまで手段だ。きれい事と言われるかもしれないが、本来的には勉強とはそうあるべきだと思う。
このような偏差値主義への批判は、偏差値ができた頃から存在したといっても過言ではない。だが、AIの台頭により、今まで感情や感性に委ねられてきた部分にまで数値競争が入り込んできている。
文字情報として発信されたものは全て、機械学習の対象になり、数値として分析可能だ。大学入学共通テストが導入された際、国語の試験で記述式回答を導入する検討がなされた。その時は「記述式問題の意義を確保しつつ、大量の回答を同一基準で採点できない」という理由で導入されなかったが、今は違う。記述式の試験をAIが採点する日もそう遠くないだろう。
「ではこうすればいい」というような解決策を持ち合わせているわけではない。この意見を声高に主張すること自体、「いいね」を獲得するための競争に巻き込まれている。だが、「学ぶ」ということが数値化され、不可逆的な競争に巻き込まれつつある、という危機感は、学生として常に持っておくべきだと思う。
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
 『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク
『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク







