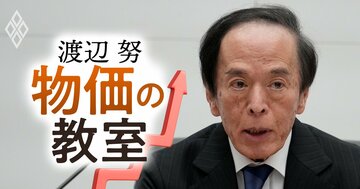日本銀行の長期国債保有比率を異次元緩和前に戻すの
に今後かかる期間。買い入れ国債残高の平均残存期間
を6~7年とし、毎月の国債買い入れオペを異次元緩和前
の月1兆~2兆円まで減額すると想定し筆者試算
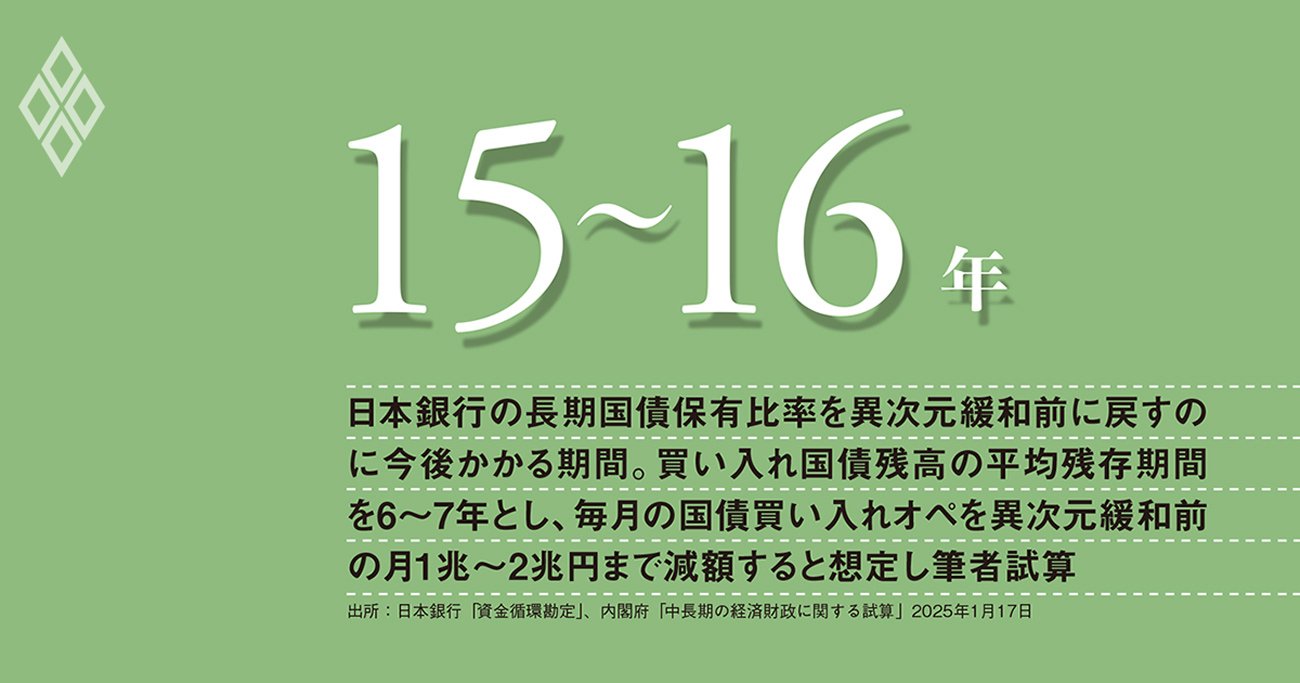
日本銀行は昨年12月の金融政策の多角的レビューで、2013年以降の異次元緩和は全体として経済にプラスの影響と評価した一方、今後副作用の影響が大きくなる可能性にも言及した。副作用の一つが国債の大量買い入れに伴うもので、日銀の長期国債の保有比率は異次元緩和前の11.5%から昨年6月には53.2%に達し、市場流動性や金利の価格発見機能が損なわれた。
日銀は昨年、国債買い入れの削減を決定し、来年3月までの削減計画を示し実施中である。次回の6月会合の中間評価で減額幅を増やす可能性は低く、関心は来年4月以降の減額幅と保有国債残高の姿にある。日銀の植田和男総裁は、減額は「決めるからには相応の規模で」とする一方で、「残高の減少ペースは極めて緩やか」としているからだ。
長期金利は市場で決まるのが原則だが、レビューによると国債保有残高の長期金利引き下げ効果は約1%ポイントだ。異次元緩和以降に下押し圧力が強まったため、金利の価格発見機能の回復には日銀の保有比率を異次元緩和前に戻すことが基本となる。今後それまでにかかる期間を、異次元緩和前の国債買い入れ額(月1兆~2兆円)まで減額し続けるとして試算すると、15~16年を要する。ただし、この期間は国債発行残高の見通し次第であり、また、毎月の買い入れ額をもっと減額したり、残高の平均残存期間を異次元緩和前(12年度は5年)に戻すとかなり短縮できる。
課題は、日銀の代わりに誰が国債を購入してくれるかだ。さまざまな試算値によると、金融規制もあって、民間金融機関の国債吸収余力は、筆者の試算した必要額の半分程度しかない。現状の国債吸収余力に合わせて市場の正常化のスピードを緩めれば、いつまでも副作用が継続・拡大しかねない。ここまでの国債保有残高拡大の付けが大き過ぎるといわざるを得ない。
日銀が金利の下押し圧力を減らして市場の正常化を促せば、海外投資家や個人の参加も期待できる。そのプロセスを混乱なく進めるためには、信頼に足る中長期的な財政健全化策に加え、国債管理政策との連携が欠かせない。
(キヤノングローバル戦略研究所 特別顧問 須田美矢子)