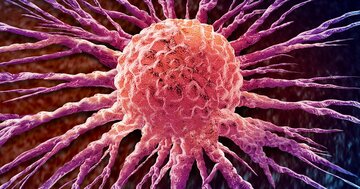逆に、タンパク質の摂取量を減らすことは、糖尿病予防のための有益な手段になりうるという結果も報告されています。
たとえば、エネルギー摂取量が同じ食事でも、タンパク質からのエネルギー量が全体の7~9パーセントとなるような食事を約6週間摂取した人(過体重~軽度肥満の中年)では、体重が2.6キログラム減少し、空腹時血糖値も低下したのに対して、タンパク質が総エネルギー摂取量の17パーセントを占めるような食事を摂取した人では、そのような効果は認められなかったという研究結果が報告されています(注2)。
ちなみに、この「総エネルギー摂取量の7~9パーセント」という値は、沖縄の百寿者のタンパク質摂取量に近い値となっています。
タンパク質を摂りすぎると
死亡率が高くなる!?
減量・ダイエットを行った際には、体脂肪量だけを減らすことが望ましいのですが、骨格筋をはじめとする除脂肪組織も減少してしまうことがあります。
そのような除脂肪組織の減少を最小限にとどめるために、減量中にはタンパク質を多く摂取することが推奨されています。
しかしながら、肥満者を対象として行われた研究では、減量期間中のタンパク質摂取量が通常の食事と同じ場合(0.8グラム/キログラム体重/日)には、体重を10パーセント減らすことで、インスリンの効き目がよくなり、血糖値が低下しやすくなった(インスリン感受性が改善した)のに対して、タンパク質量の多い食事(1.3グラム/キログラム体重/日)を摂取しながら減量を行った肥満者ではそのような効果が得られなかったことが報告されています(注3)。
つまり、タンパク質を多く摂取した肥満者では、体重や内臓脂肪が顕著に減少したにもかかわらず、依然として2型糖尿病の発症リスクが高いままだったのです。
さらに、アメリカで行われた国民健康・栄養調査においても、高タンパク質食(総エネルギー摂取量のうち20パーセントもしくはそれ以上がタンパク質で構成されているような食事)を摂取している50~65歳の男女では、低タンパク質食を摂取している人たちに比べて、18年間の追跡調査期間中における死亡率が75パーセントほど高く、さらにがんおよび糖尿病による死亡率も4倍高かったことが報告されています(注4)。
(注3)Smith, G.I. et al., Cell Reports, 17:849-861, 2016.
(注4)Levine, M.E. et al., Cell Metabolism, 19:407-417, 2014.