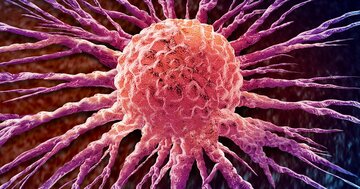以上のように、確かに骨格筋量を増やすという点においては、タンパク質を多く摂取することが効果的といえそうですが、その一方で、糖尿病の発症率や死亡率といった点においては、むしろ好ましくない影響をもたらす可能性があることが示唆されています。
体のある一部の機能に対して優れた効果が得られることが報告されると、私たちは、その栄養素を少しでも多く摂取しようとします。しかしながら、その栄養素を過剰に摂取することで、別の部分ではむしろ悪影響が生じる可能性もあります。
したがって、世間で有効だといわれている栄養素に関しても、「他の部分に対してはどのような影響があるのか?」ということに注意を払いながら、摂取量を増やすべきか否かを冷静に判断する必要があります。
「筋肉を増やすために、タンパク質を多く摂ればよい」と単純に考えるのではなく、自分の体質や状況(筋量を増やすことを優先すべき状態なのか?それとも糖尿病などの代謝性疾患の発症を予防すべき状態なのか?)を見極めながら、その摂取量を調整しましょう。
タンパク質は具体的に
どのくらい摂取したらよい?
以上のように、タンパク質に関しては、「骨格筋を増やす」という効果にばかり注目が集まり、その摂取量を増やそうという考え方が広まる一方で、摂取量を増やすことによって生じる悪影響に対しては、ほとんど注意が払われていないようです。
では、タンパク質はどのくらい摂取すべきなのでしょうか?
前述のような研究結果をもとに、健康長寿を実現するためには、タンパク質の摂取量を総エネルギー摂取量の10パーセント程度までにして、さらに炭水化物とタンパク質の摂取比率を、炭水化物:タンパク質=10:1程度にすべきであるという意見が示されています(注6)。
この「総エネルギー摂取量の10パーセント」というのは、タンパク質何グラムくらいになるのでしょうか?
「日本人の食事摂取基準」では、1日の推定エネルギー必要量は、身体活動量が「普通」の成人男女でそれぞれ約2600キロカロリーと2000キロカロリーとなっています。したがって、タンパク質をそのうちの10パーセント程度とすると、男性で260キロカロリー、女性で200キロカロリーとなります。
タンパク質1グラムは4キロカロリーですので、成人男女でそれぞれおよそ65グラムと50グラムという計算になります。この値は、「日本人の食事摂取基準」で示されている推奨量とほぼ同じ値となります。